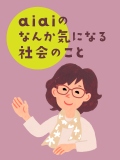記事・レポート
ビジネスとクリエイティブの新しい関係
ライフスタイルサロン「編集力シリーズ」第二回 ゲスト:佐藤可士和
更新日 : 2009年09月03日
(木)
第8章 日本のプレゼンスを高めるための仕組みへの期待

竹中平蔵: 極端な両面があると思います。結果的に素人みたいな人にいくのが1つ、もう1つは実績のあるところにだけいってしまう。
公共事業が典型です。「入札したことがあること」が入札の必要資格では、新規参入なんていつまでたってもできません。同じように文化予算も、権威があるといわれている人が「いい」と評価した人や、その人の弟子ばかりにお金がいくという現実があります。
マーケットが答えを出してくれるものはそれでいいと思うのですが、公共事業はマーケットが答えを出してくれませんから、新しいチェックの仕組みが必要なんでしょうね。それは結局、「アウトカムを出して、それが達成されたかどうかをチェックする」という当たり前のことなのですが、それができないんですよね。
佐藤可士和: 日本は国際社会の中でまだまだポテンシャルがあると思うので、民間は勝手にやっていればいいわけですが、国としてのクリエイションを世界に出していくときに、一番いい状態でプレゼンテーションできるような仕組みをつくらないと恥ずかしいというか、もったいないことになるのは嫌ですね。
竹中平蔵: 結果がうまくいかなかったら、政治が責任をとらなければならない。でもそれが嫌だから、実績のある人や有名大学の何とかさんに任せる、というのは政治家の責任逃れです。
公共事業が典型です。「入札したことがあること」が入札の必要資格では、新規参入なんていつまでたってもできません。同じように文化予算も、権威があるといわれている人が「いい」と評価した人や、その人の弟子ばかりにお金がいくという現実があります。
マーケットが答えを出してくれるものはそれでいいと思うのですが、公共事業はマーケットが答えを出してくれませんから、新しいチェックの仕組みが必要なんでしょうね。それは結局、「アウトカムを出して、それが達成されたかどうかをチェックする」という当たり前のことなのですが、それができないんですよね。
佐藤可士和: 日本は国際社会の中でまだまだポテンシャルがあると思うので、民間は勝手にやっていればいいわけですが、国としてのクリエイションを世界に出していくときに、一番いい状態でプレゼンテーションできるような仕組みをつくらないと恥ずかしいというか、もったいないことになるのは嫌ですね。
竹中平蔵: 結果がうまくいかなかったら、政治が責任をとらなければならない。でもそれが嫌だから、実績のある人や有名大学の何とかさんに任せる、というのは政治家の責任逃れです。


1人当たりのGDPなどを見る限り、日本経済の力は明らかに落ちているのですが、経済の影に隠れていた文化の力が相対的に見直されているというのは、間違いなく事実です。今、伝統文化だけではなく、広い意味での文化が表に出てくるチャンスを迎えていると思います。文化予算も増やさなければいけないし、コンセプトリーダーみたいな人、まさに可士和さんみたいな人が文化に関してもっとたくさん出てきてほしいと思います。
佐藤可士和: 日本人のコミュニケーション下手なところが、侘びや寂びのような複雑な概念を生んでいるのですが、国として、世界の中でコミュニケーションを相当戦略的にやっていかないともったいない。
竹中平蔵: そういう中で、英語という最低限の入口をクリアしなければいけないのですが、今、アジアの各国の中で日本の英語教育が一番遅れていると思います。
佐藤可士和: 実は僕も英語には苦労しています。以前どこかのリゾートで、特に英才教育を受けたわけではない掃除係のおばさんがフランス語を読んで、英語でしゃべっていたんです。日本では、わざとしゃべれなくしようとしているんじゃないかとか、何か大きな意思が働いているんじゃないか、ぐらいに思うのですが(笑)、そんなことないですか?
竹中平蔵: これはカルチャーのバリアもあると思います。私はインドはすごい国になると思うのですが、その最大のポイントは、やはり英語力です。我々は「英語が下手だ」と言うじゃないですか。下手でいいんですよ。そういうバリアをまず超えなければいけないし、教育制度も変えなければいけない。コミュニケートする手段としては、現実にこれしかないんだから、ちゃんと受け入れようと。これもやはりBack to Basicだと思うのです。
安藤礼二: あっという間に時間が来てしまいました。デザインプロジェクトからナショナルデザインまで、基本に戻って本質をつかむことによって未知なるものに達する。これがまさに編集力ということではないでしょうか。今日は本当にありがとうございました。(終)
佐藤可士和: 日本人のコミュニケーション下手なところが、侘びや寂びのような複雑な概念を生んでいるのですが、国として、世界の中でコミュニケーションを相当戦略的にやっていかないともったいない。
竹中平蔵: そういう中で、英語という最低限の入口をクリアしなければいけないのですが、今、アジアの各国の中で日本の英語教育が一番遅れていると思います。
佐藤可士和: 実は僕も英語には苦労しています。以前どこかのリゾートで、特に英才教育を受けたわけではない掃除係のおばさんがフランス語を読んで、英語でしゃべっていたんです。日本では、わざとしゃべれなくしようとしているんじゃないかとか、何か大きな意思が働いているんじゃないか、ぐらいに思うのですが(笑)、そんなことないですか?
竹中平蔵: これはカルチャーのバリアもあると思います。私はインドはすごい国になると思うのですが、その最大のポイントは、やはり英語力です。我々は「英語が下手だ」と言うじゃないですか。下手でいいんですよ。そういうバリアをまず超えなければいけないし、教育制度も変えなければいけない。コミュニケートする手段としては、現実にこれしかないんだから、ちゃんと受け入れようと。これもやはりBack to Basicだと思うのです。
安藤礼二: あっという間に時間が来てしまいました。デザインプロジェクトからナショナルデザインまで、基本に戻って本質をつかむことによって未知なるものに達する。これがまさに編集力ということではないでしょうか。今日は本当にありがとうございました。(終)
関連リンク
ビジネスとクリエイティブの新しい関係 インデックス
-
第1章 編集とは、対象を整理して本質を導きだすこと
2009年05月20日 (水)
-
第2章 コミュニケーション戦略で結果が変わる
2009年06月05日 (金)
-
第3章 編集力でブランドの本質を磨き上げる
2009年06月25日 (木)
-
第4章 デザインの力を未知の分野に
2009年07月13日 (月)
-
第5章 発想のダイナミズムと制約との調和
2009年07月28日 (火)
-
第6章 外からの刺激が発想をプログレスする
2009年08月11日 (火)
-
第7章 日本のよさを国際社会の中で伝えられない政治力
2009年08月24日 (月)
-
第8章 日本のプレゼンスを高めるための仕組みへの期待
2009年09月03日 (木)
注目の記事
-
04月22日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年4月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の"いま"が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
04月22日 (火) 更新
aiaiのなんか気になる社会のこと
「aiaiのなんか気になる社会のこと」は、「社会課題」よりもっと手前の「ちょっと気になる社会のこと」に目を向けながら、一市民としての視点や選....
-
04月22日 (火) 更新
米大学卒業式の注目スピーチから得られる学び<イベントレポート>
ニューヨークを拠点に地政学リスク分析の分野でご活躍され、米国社会、日本社会を鋭く分析されているライターの渡邊裕子さんに、アメリカの大学の卒業....
現在募集中のイベント
-
開催日 : 05月19日 (月) 12:30~14:15
ジェラルド・カーティス氏 特別講演「これからの民主主義」
コロンビア大学政治学名誉教授のジェラルド・カーティス氏をお迎えし、トランプ政権の今後の展望と、これからの民主主義の可能性についてご講演いただ....