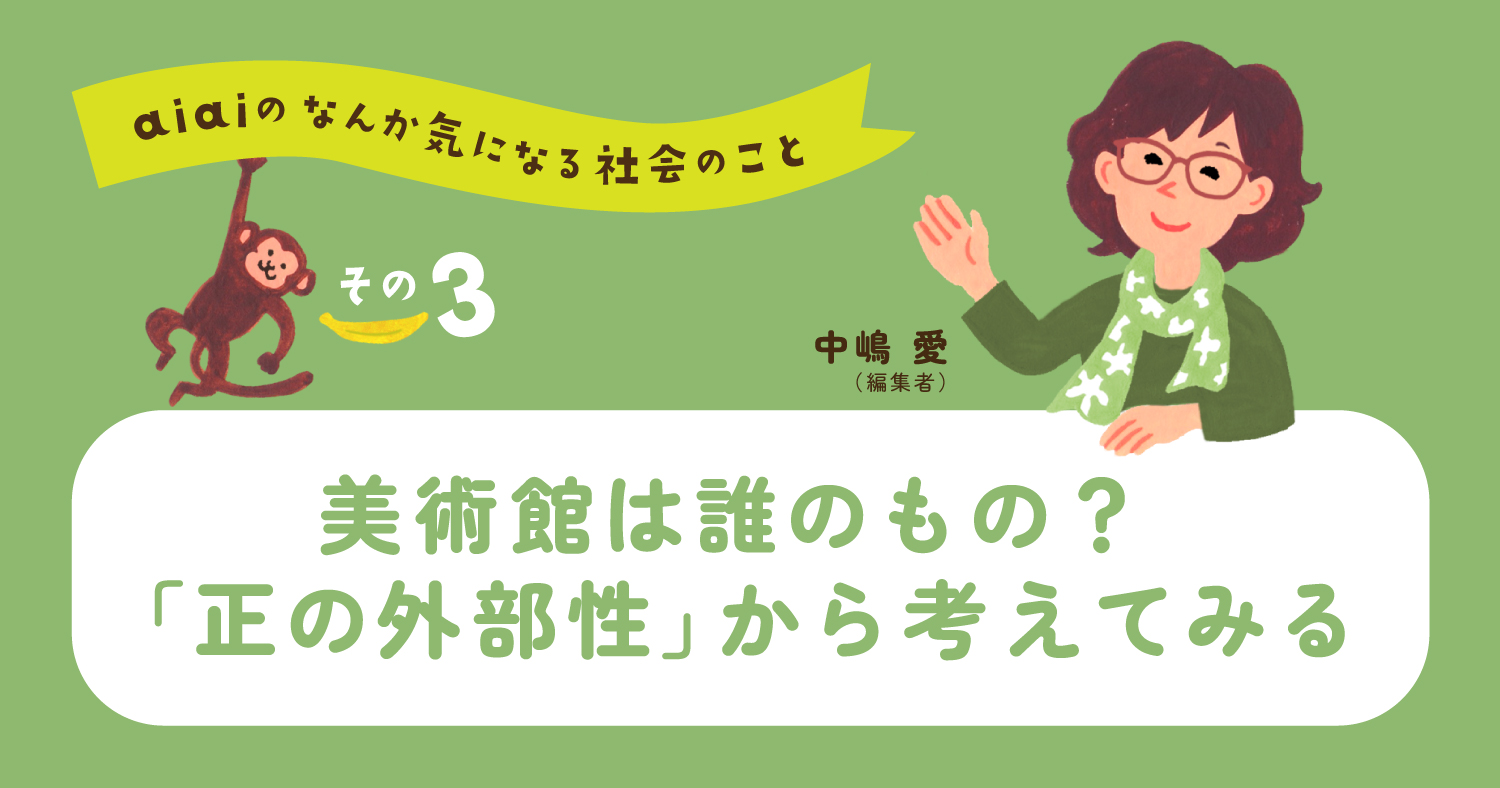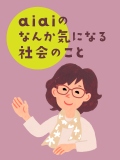記事・レポート
aiaiのなんか気になる社会のこと
【第10回】柳宗悦の蒐集論がおしえてくれること
私欲が利他に転換するとき
更新日 : 2025年04月22日
(火)
【第10回】柳宗悦の蒐集論がおしえてくれること 私欲が利他に転換するとき
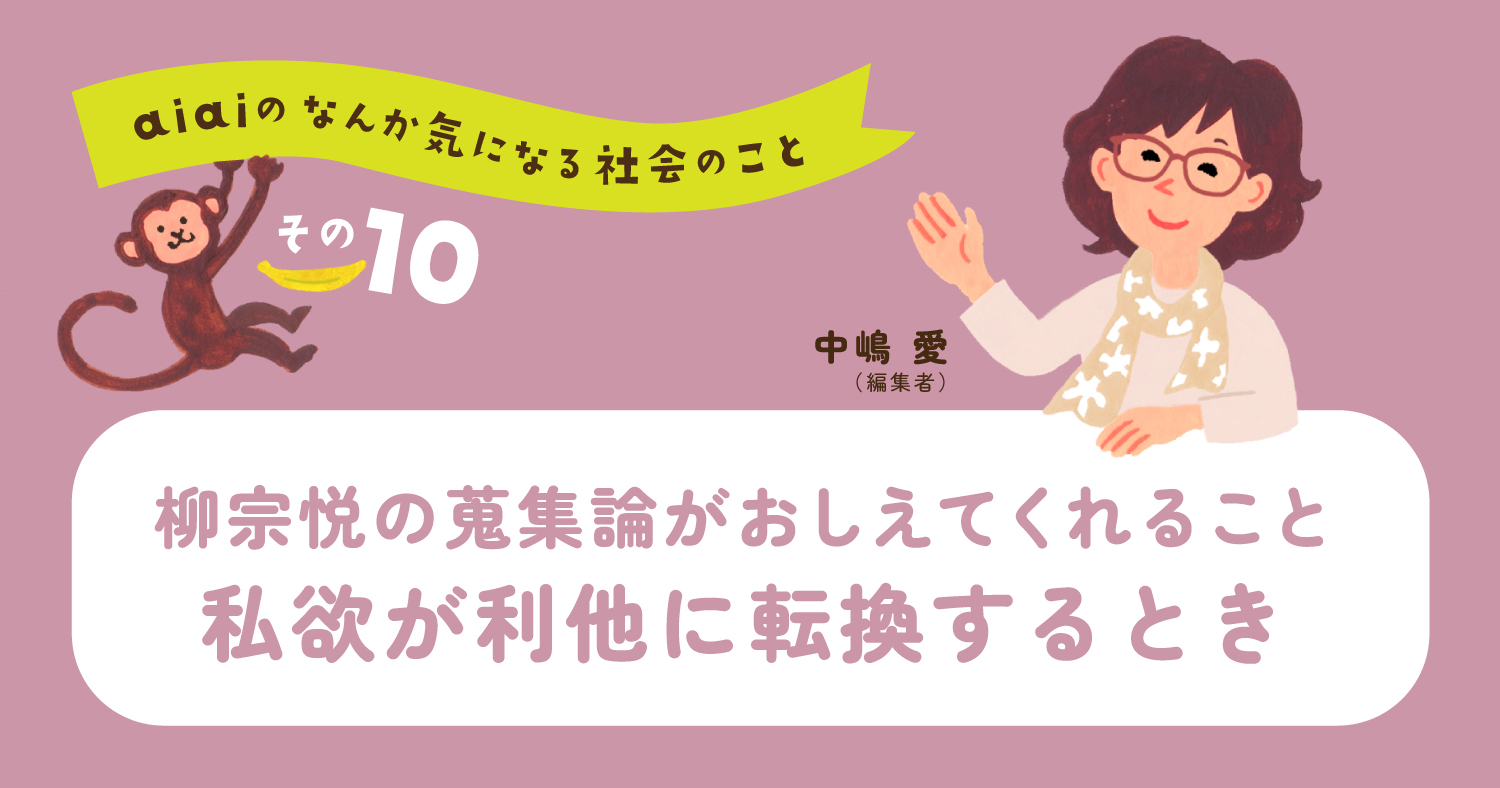
春と冬が綱引きをしているような激しい寒暖差にみまわれた3月末から4月初旬にかけて、鳥取県と長野県を旅した。あらかじめ計画していたわけではないが、都合5つの美術館を巡った。まずは開館したばかりの鳥取県立美術館。庭園が有名な島根県の足立美術館、鳥取民藝美術館、そして長野では松本工藝館と長野県立美術館を訪ねた。
鳥取県立美術館は都道府県が直接運営する美術館としては最後発に近い。善光寺の隣に建つ長野県立美術館も2021年に全面改装した真新しい建物だ。どちらも周囲の街並みに調和したすばらしい建物で、バリアフリー対応はもちろん、多目的スペース、カフェやショップなどの施設も充実している。現代の公立美術館(博物館)は、たんに美術作品や関連資料を収蔵展示するだけでなく、まちづくりや産業、福祉といった機能の一部をも担う。さらに、「一般に公開され、誰もが利用でき、包摂的であって、多様性と持続可能性を育む」という一文が、ミュージアムの定義として2022年に国際博物館会議(ICOM)によって加えられたこともあって、美術館の社会的役割はどんどん広範なものになっている。
足立美術館は貧しい小作農の出ながら不動産投資などで成功し、一代で財を築いた実業家の足立全康が、事業の傍ら集めてきた近代日本絵画のコレクションを展示するために私財をつぎ込んでつくった美術館である。横山大観のコレクションが有名で、「日本一美しい庭園(*)」として知られる庭も大観の絵を3Dで再現したものだ。大観の「那智の滝」を再現するために、庭園後方にある山になんと人工の滝までつくってしまった。開館当時は名もない美術館に訪れる人はほとんどいなかったが、足立は諦めず、規模を倍にして天皇陛下を招致することを思いつき、これを実現させてしまう。美術館の売店で買い求めた『戦前の日本の金持ち』(出口治明編)にあるエピソードだ。さらに足立は日本開発銀行を口説き、「地方開発融資」の名目で初めて美術館への融資をとりつけることに成功した。そのときの口説き文句は「国がやるべき仕事をか弱い私どもがやっています」だったという。「か弱い」かどうかは別として、文化事業は本来国がやるべき仕事であり、それを自分はやっているのだという強烈な自負を感じさせる言葉だ。
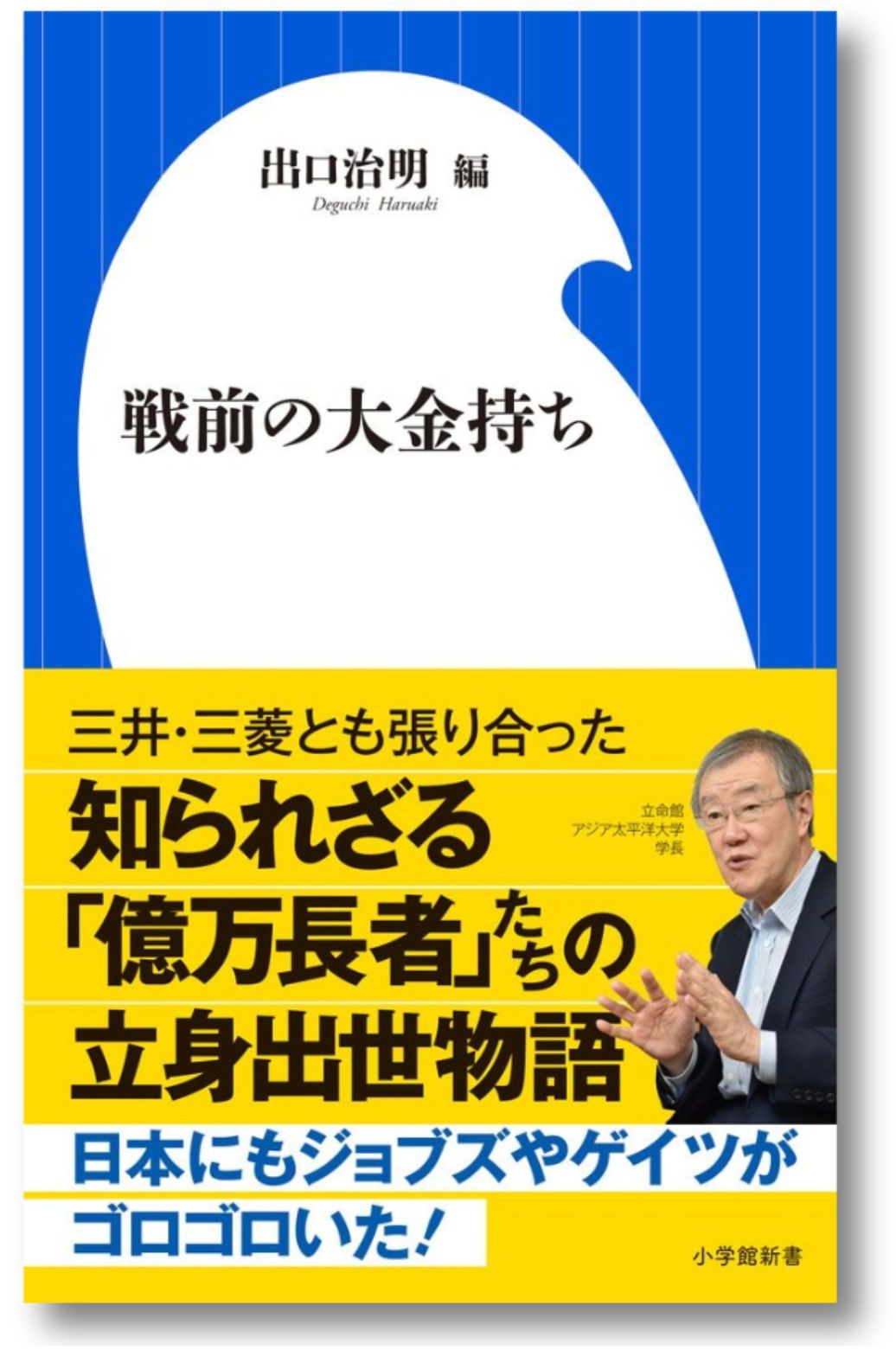
開館から半世紀を過ぎ、「世界一の日本庭園」には海外からも人が押し寄せ、最寄りの駅からは無料の送迎バスまで出る。実際、わたしも「鳥取まで来たのだからあそこにも行っておこう」と旅程を伸ばして足を運んだのだった。一部の隙もなく手入れされた庭園には侘び寂びを感じないとか、大観ばかりでほかに見るものがないといった評価も一部にはあるものの、主亡き後もこうして文化資産、観光資源として持続しているところに、たんなる金持ちの道楽ではなく、一種の公共事業としての意義を見出すことができよう。足立美術館は設立以来、財団法人足立美術館が運営している。
何度かリバイバルブームを繰り返しながら今なお根強い人気のある民藝。鳥取と松本は、1920年代に柳宗悦らの呼びかけで日本各地にひろがった民藝運動のネットワークにおけるハブである。鳥取民藝美術館は柳と共に初期の民藝運動を牽引した吉田璋也が自身のコレクションを展示するためにつくった土蔵風の建物で、医師である吉田の職場であった医院の向かい側に建っている。並びには日本初の民藝専門店と、民藝の器で郷土料理を出す割烹がある。吉田は医院として使う建物を自ら設計し、そこにも民藝の意匠を散りばめた。生活の中の美という民藝を実践した人である。
松本民芸館は、民藝運動に傾倒した丸山太郎が日本のみならず世界中から民芸品を買い集めて独力で作った美術館だ。丸山はもともと民芸品店(現在も営業を続けている「ちきりや」)を営み、自身も精巧な卵殻細工を得意とする作家だった。市の中心部から離れているにもかかわらず、国内外から人が訪れる。丸山は、没後はコレクションと建物を松本市に寄贈し、現在は市が所有し運営しているので個人美術館ではなくなったが、丸山太郎の残した姿を忠実に守っている。
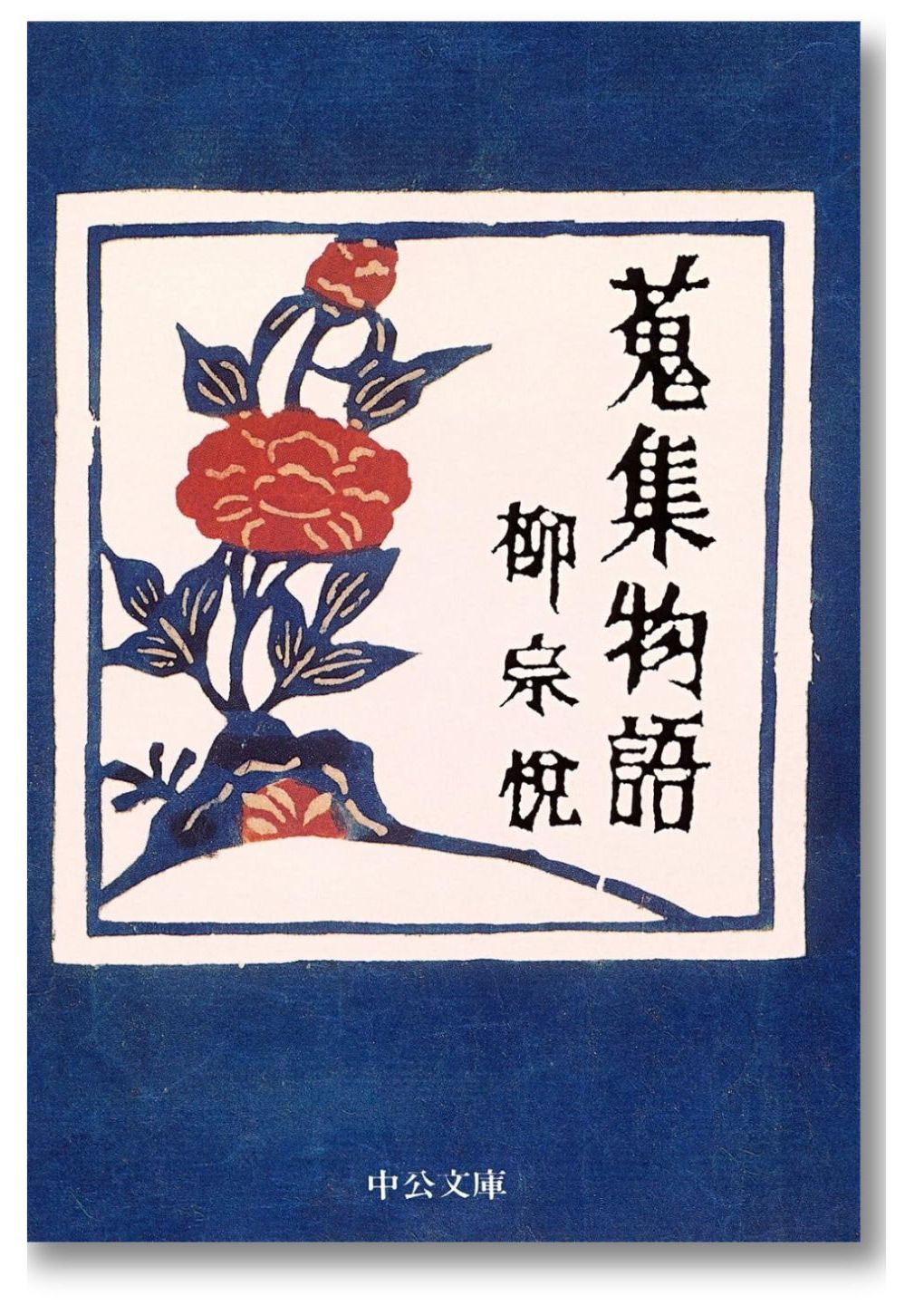
この松本民芸館に行く途中で立ち寄った古本屋で偶然手にしたのが、柳宗悦の『蒐集物語』という本だ。柳の膨大なコレクションのなかでもとくに思い入れのある品々をどうやって手に入れたかというエッセイが収録されていて、それがことごとく面白い。たとえば次のような話がある。骨董屋に取り置きを頼んでおいた盒子を引き取りにいったらほかの客に売られていて大いに落胆したが、数年後に知り合いの家でそれを偶然見つけた。自分が欲しかったものだと言いだせないまままた時が過ぎ、その知り合いが亡くなった後、アメリカのボストン近郊の骨董屋でその盒子に三度巡り合い、15年越しで手に入れた。他にも骨董市で競り負けたのが悔しくて落札した人を突き止めて手に入れようとしたとか、自分はお金がないのでほかの人にお願いして買ってもらうなど、とにかくこれはと思ったものへの執着がすさまじい。それだけでなく見境のない買い物といわれることに対して言い訳をしたり、自身の審美眼は絶対だとうそぶいたりしていて、柳宗悦という人の素顔が生き生きと伝わってくる。美や美意識を語って教養人然としている柳宗悦より、欲しいと思ったものが手に入らないとねちねちと執着し、首尾よく手に入ったときには有頂天で小躍りしているような柳宗悦のほうが私は好きである。
3月31日に、以前このコラムで書いた(「美術館は誰のもの?」)DIC川村記念美術館が千葉県佐倉で34年の歴史に幕を下ろした。今後、コレクションを四分の一ほどに縮小したうえで公益財団法人国際文化会館に移転する。マーク・ロスコの〈シーグラム壁画〉を収容するための特別室を新設することも決まっている。公益財団法人との連携は考えうる選択肢のなかで最良のものだったと思われる。DICの主要株主である投資ファンド、オアシス・マネジメントは、本業に関係のない美術品の保有を不適切として、この「縮小移転」にも反対している。DIC川村記念美術館のコレクションは、広大な庭と貴族の別荘のような建物と一体のものだったから、コレクションの一部は守られたとしても、それは「縮小移転」ではなく限りなく事実上の閉鎖である。
佐倉のDIC川村記念美術館を一度でも訪れたことがある人なら、創設者の川村勝巳(第二代社長)の蒐集と美術館建設への熱狂は柳宗悦や足立全康のそれに劣らぬ熱量であったことがわかるだろう。しかし個人の熱狂が世代交代によって、わかりやすい価値に還元されてしまうのは世の常である。そうならないためには、私欲、私有を、利他、共有へ変換するための準備や仕組みが必要だ。
*アメリカの日本庭園専門誌 Sukiya Living Magazine: The Journal of Japanese Gardening による日本国内の日本庭園1000カ所のランキングで、2024年まで22年連続日本一に選ばれている。
執筆者:中嶋 愛
Glass Rockプログラムディレクター。編集者。ビジネス系出版社で雑誌、単行本、ウェブコンテンツの編集に携わったのち、ソーシャルイノベーションの専門誌、Stanford Social Innovation Reviewの日本版立ち上げに参画。「スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版」創刊編集長。スタンフォード大学修士修了。同志社大学客員教授。庭と建築巡りが好きです。
鳥取県立美術館は都道府県が直接運営する美術館としては最後発に近い。善光寺の隣に建つ長野県立美術館も2021年に全面改装した真新しい建物だ。どちらも周囲の街並みに調和したすばらしい建物で、バリアフリー対応はもちろん、多目的スペース、カフェやショップなどの施設も充実している。現代の公立美術館(博物館)は、たんに美術作品や関連資料を収蔵展示するだけでなく、まちづくりや産業、福祉といった機能の一部をも担う。さらに、「一般に公開され、誰もが利用でき、包摂的であって、多様性と持続可能性を育む」という一文が、ミュージアムの定義として2022年に国際博物館会議(ICOM)によって加えられたこともあって、美術館の社会的役割はどんどん広範なものになっている。
創設者の個性が惹きつける個人美術館
大変結構なことだと思う一方で、多機能化すればするほど美術館の個性というものは発揮しにくくなる。公共性と個性というものはもとより両立しづらいものだ。そういう意味でいえば、今回の旅で訪れた3つの個人美術館は、創設者の個性というかエゴが充満しているような場所だった。しかしそのエゴは社会や未来に向けられていて、結果としてエゴの殿堂がコモンズのような存在として多くの人をひきつけ、存続し続けているのは不思議なことである。足立美術館は貧しい小作農の出ながら不動産投資などで成功し、一代で財を築いた実業家の足立全康が、事業の傍ら集めてきた近代日本絵画のコレクションを展示するために私財をつぎ込んでつくった美術館である。横山大観のコレクションが有名で、「日本一美しい庭園(*)」として知られる庭も大観の絵を3Dで再現したものだ。大観の「那智の滝」を再現するために、庭園後方にある山になんと人工の滝までつくってしまった。開館当時は名もない美術館に訪れる人はほとんどいなかったが、足立は諦めず、規模を倍にして天皇陛下を招致することを思いつき、これを実現させてしまう。美術館の売店で買い求めた『戦前の日本の金持ち』(出口治明編)にあるエピソードだ。さらに足立は日本開発銀行を口説き、「地方開発融資」の名目で初めて美術館への融資をとりつけることに成功した。そのときの口説き文句は「国がやるべき仕事をか弱い私どもがやっています」だったという。「か弱い」かどうかは別として、文化事業は本来国がやるべき仕事であり、それを自分はやっているのだという強烈な自負を感じさせる言葉だ。
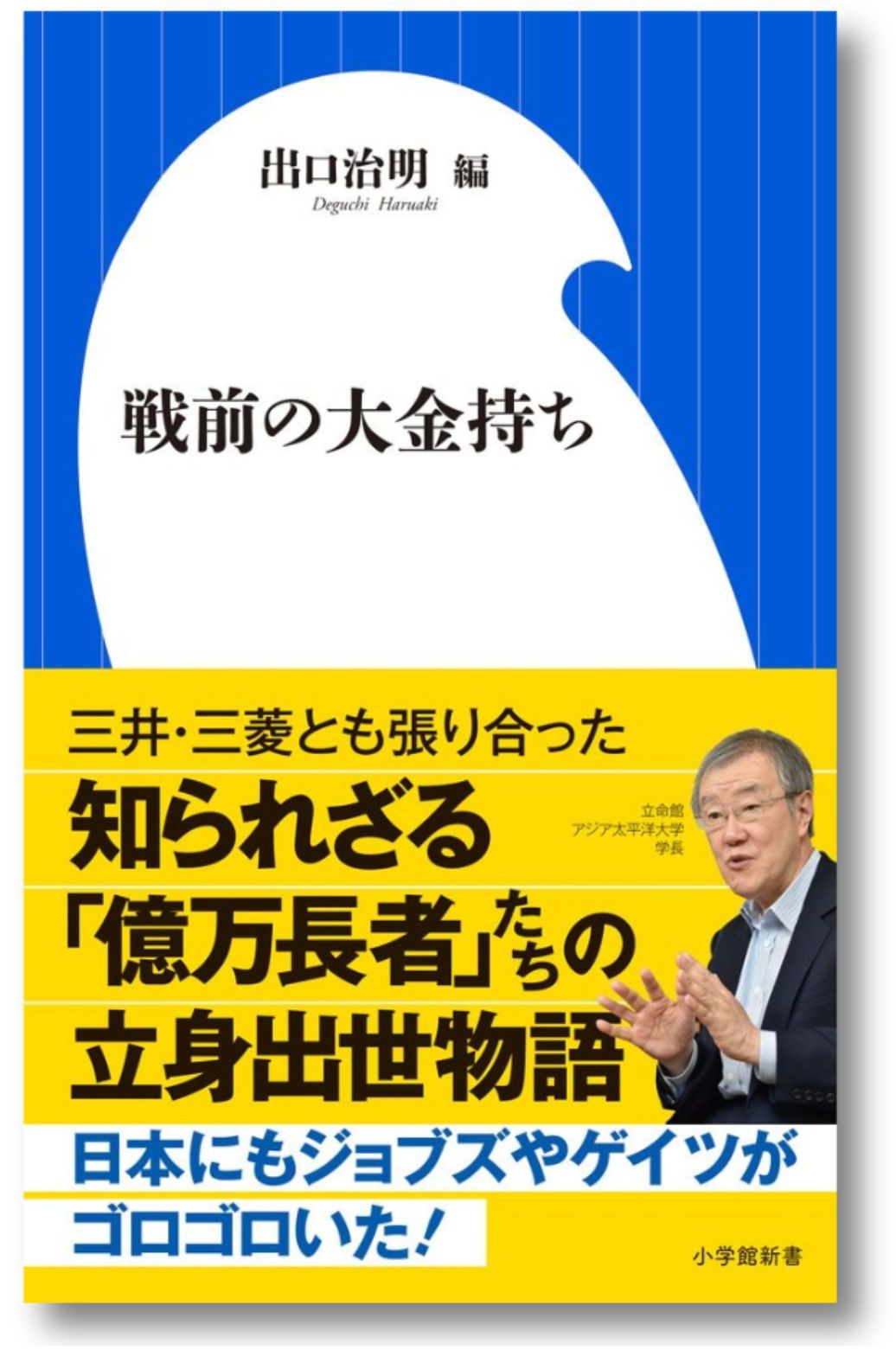
開館から半世紀を過ぎ、「世界一の日本庭園」には海外からも人が押し寄せ、最寄りの駅からは無料の送迎バスまで出る。実際、わたしも「鳥取まで来たのだからあそこにも行っておこう」と旅程を伸ばして足を運んだのだった。一部の隙もなく手入れされた庭園には侘び寂びを感じないとか、大観ばかりでほかに見るものがないといった評価も一部にはあるものの、主亡き後もこうして文化資産、観光資源として持続しているところに、たんなる金持ちの道楽ではなく、一種の公共事業としての意義を見出すことができよう。足立美術館は設立以来、財団法人足立美術館が運営している。
何度かリバイバルブームを繰り返しながら今なお根強い人気のある民藝。鳥取と松本は、1920年代に柳宗悦らの呼びかけで日本各地にひろがった民藝運動のネットワークにおけるハブである。鳥取民藝美術館は柳と共に初期の民藝運動を牽引した吉田璋也が自身のコレクションを展示するためにつくった土蔵風の建物で、医師である吉田の職場であった医院の向かい側に建っている。並びには日本初の民藝専門店と、民藝の器で郷土料理を出す割烹がある。吉田は医院として使う建物を自ら設計し、そこにも民藝の意匠を散りばめた。生活の中の美という民藝を実践した人である。
松本民芸館は、民藝運動に傾倒した丸山太郎が日本のみならず世界中から民芸品を買い集めて独力で作った美術館だ。丸山はもともと民芸品店(現在も営業を続けている「ちきりや」)を営み、自身も精巧な卵殻細工を得意とする作家だった。市の中心部から離れているにもかかわらず、国内外から人が訪れる。丸山は、没後はコレクションと建物を松本市に寄贈し、現在は市が所有し運営しているので個人美術館ではなくなったが、丸山太郎の残した姿を忠実に守っている。
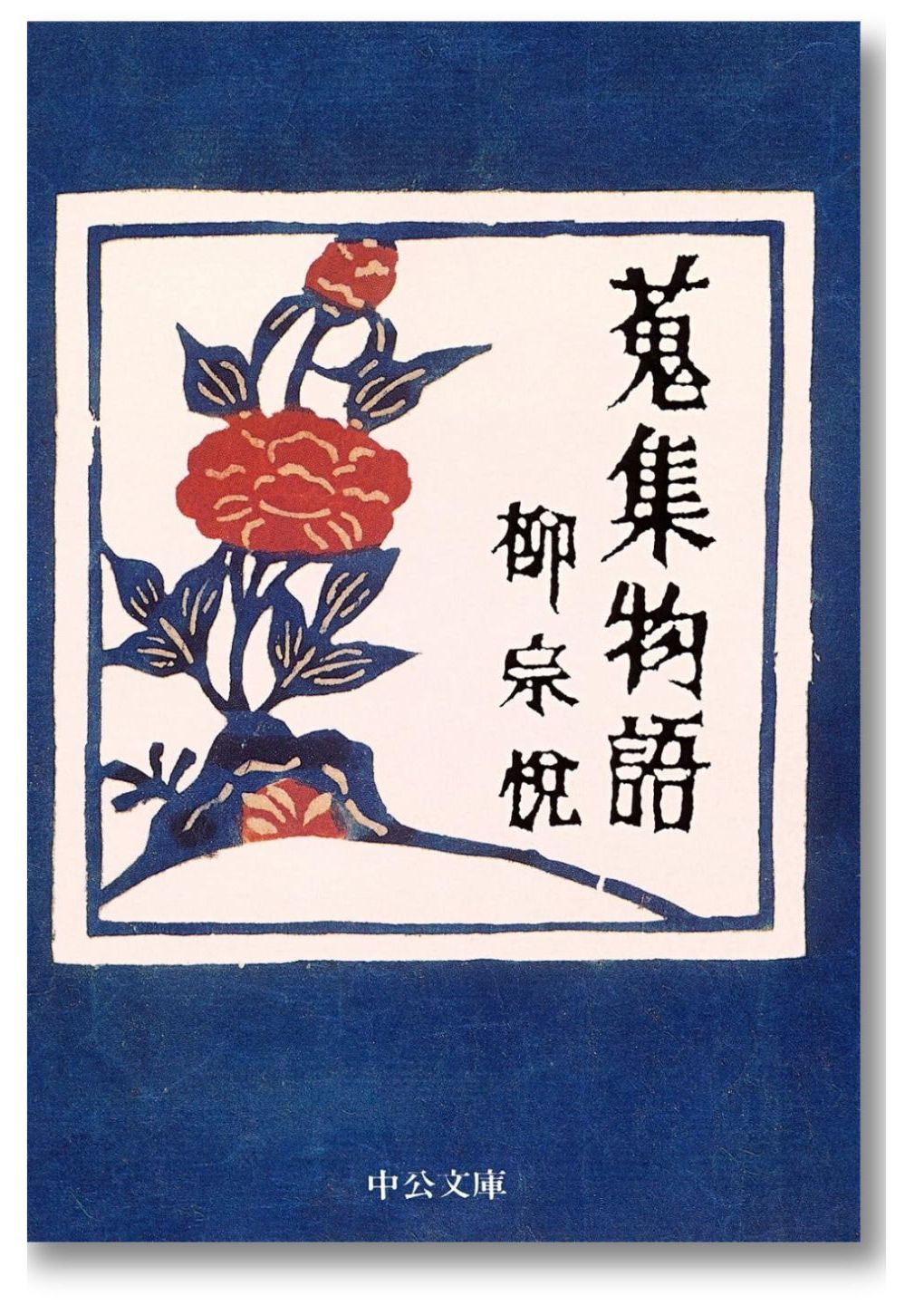
この松本民芸館に行く途中で立ち寄った古本屋で偶然手にしたのが、柳宗悦の『蒐集物語』という本だ。柳の膨大なコレクションのなかでもとくに思い入れのある品々をどうやって手に入れたかというエッセイが収録されていて、それがことごとく面白い。たとえば次のような話がある。骨董屋に取り置きを頼んでおいた盒子を引き取りにいったらほかの客に売られていて大いに落胆したが、数年後に知り合いの家でそれを偶然見つけた。自分が欲しかったものだと言いだせないまままた時が過ぎ、その知り合いが亡くなった後、アメリカのボストン近郊の骨董屋でその盒子に三度巡り合い、15年越しで手に入れた。他にも骨董市で競り負けたのが悔しくて落札した人を突き止めて手に入れようとしたとか、自分はお金がないのでほかの人にお願いして買ってもらうなど、とにかくこれはと思ったものへの執着がすさまじい。それだけでなく見境のない買い物といわれることに対して言い訳をしたり、自身の審美眼は絶対だとうそぶいたりしていて、柳宗悦という人の素顔が生き生きと伝わってくる。美や美意識を語って教養人然としている柳宗悦より、欲しいと思ったものが手に入らないとねちねちと執着し、首尾よく手に入ったときには有頂天で小躍りしているような柳宗悦のほうが私は好きである。
「悦び合える悦びは、何ものにもまさって吾々には幸福なのだ」
民藝運動による素朴な美の礼賛には、エリート主義、植民地主義的パターナリズムが見え隠れしているという批判もあるが、名もなき者たちの手仕事のなかに究極の美を見出した柳宗悦という個人の熱狂は、日本各地に、さらには海のむこうにまで伝播してひとつの「運動」となり、それぞれの地の熱狂者のネットワークが生まれた。彼らが民藝品を集めたのは、自分一人で愛でるためではなく、それまで誰も目を向けることのなかった「下手物」のなかから見つけ出した美しいものをお互いに褒め合う悦びのためだった。柳はこれはと思うものを手に入れたときには真っ先に河井寛次郎、濱田庄司、芹沢銈介ら近しい仲間に連絡して見せた。「悦び合える悦びは、何ものにもまさって吾々には幸福なのだ」と柳は言う。「一人で感心したのでは感心し足りない。一緒に感心して初めて感心する悦びを感じる」。柳が蒐集するのは将来値上がりするからとか、自分だけで独占したいとか、富を誇示したいからではなかった。そういう意味で利己的でありながら利他的な蒐集なのである。実際、柳は『蒐集物語』のなかで、こんなふうにも言っている。「よい蒐集は、私事ではない。所有を単なる私有に止めてはならない」。さらにすすんでこうも言う。「蒐集は私有に生い立つが、進んでそれを公開し、または美術館に納めることは、一つの美学である。それが私有物から共有物に進むからである」。蒐集とは『個人の価値』であるより、『集められた価値』である
なぜ共有物にすることが大事なのか。それは「個人的蒐集は特殊な事情がない限り、いつか離散の命運をうける」からだ。「子孫への信頼は期待が出来ない。蒐集とは『個人の価値』であるより、『集められた価値』である。公共のものに移ることは、その価値への全き保障である」。このために柳らは日本民藝館を財団法人として建設した。それをもって「たとえ個人は世を去っても蒐集は永続される。私有に終わらせず、公有のものとして世に送り得る」のだ。足立全康が、自分は国のやるべき仕事を国にかわってやっているのだといきまいたのと通じるところがある。足立のように莫大な財力によって名画を買い集める富豪コレクターたちを柳は天敵のごとく嫌っていたから、いっしょにしてほしくないとは思うが。3月31日に、以前このコラムで書いた(「美術館は誰のもの?」)DIC川村記念美術館が千葉県佐倉で34年の歴史に幕を下ろした。今後、コレクションを四分の一ほどに縮小したうえで公益財団法人国際文化会館に移転する。マーク・ロスコの〈シーグラム壁画〉を収容するための特別室を新設することも決まっている。公益財団法人との連携は考えうる選択肢のなかで最良のものだったと思われる。DICの主要株主である投資ファンド、オアシス・マネジメントは、本業に関係のない美術品の保有を不適切として、この「縮小移転」にも反対している。DIC川村記念美術館のコレクションは、広大な庭と貴族の別荘のような建物と一体のものだったから、コレクションの一部は守られたとしても、それは「縮小移転」ではなく限りなく事実上の閉鎖である。
佐倉のDIC川村記念美術館を一度でも訪れたことがある人なら、創設者の川村勝巳(第二代社長)の蒐集と美術館建設への熱狂は柳宗悦や足立全康のそれに劣らぬ熱量であったことがわかるだろう。しかし個人の熱狂が世代交代によって、わかりやすい価値に還元されてしまうのは世の常である。そうならないためには、私欲、私有を、利他、共有へ変換するための準備や仕組みが必要だ。
*アメリカの日本庭園専門誌 Sukiya Living Magazine: The Journal of Japanese Gardening による日本国内の日本庭園1000カ所のランキングで、2024年まで22年連続日本一に選ばれている。
執筆者:中嶋 愛
Glass Rockプログラムディレクター。編集者。ビジネス系出版社で雑誌、単行本、ウェブコンテンツの編集に携わったのち、ソーシャルイノベーションの専門誌、Stanford Social Innovation Reviewの日本版立ち上げに参画。「スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版」創刊編集長。スタンフォード大学修士修了。同志社大学客員教授。庭と建築巡りが好きです。
参考文献
戦前の大金持ち
出口 治明小学館
蒐集物語
柳 宗悦中央公論新社
aiaiのなんか気になる社会のこと インデックス
-
【第1回】ドラッカー曰く「世界最古のNPOは日本のお寺?!」
2024年07月23日 (火)
-
【第2回】「コンヴィヴィアリティ」の視点で、厳しい暑さを乗り切るには?
2024年08月21日 (水)
-
【第3回】美術館は誰のもの?「正の外部性」から考えてみる
2024年09月24日 (火)
-
【第4回】「15分都市」という選択 住み心地のいい街の条件とは?
2024年10月22日 (火)
-
【第5回】私たちは「コモングッド」を取り戻せるか
2024年11月20日 (水)
-
【第6回】世の中は「虚構」で成り立っているという衝撃
2024年12月24日 (火)
-
【第7回】政治の話は嫌いですか ~ポリティカルイノベーション事始め~
2025年01月21日 (火)
-
【第8回】「コーヒーの一生」から見えてくる風景
2025年02月25日 (火)
-
【第9回】なぜ日本の学校では子どもたちが掃除をするのか
2025年03月25日 (火)
-
【第10回】柳宗悦の蒐集論がおしえてくれること
私欲が利他に転換するとき
2025年04月22日 (火)
注目の記事
-
04月22日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年4月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の"いま"が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
04月22日 (火) 更新
aiaiのなんか気になる社会のこと
「aiaiのなんか気になる社会のこと」は、「社会課題」よりもっと手前の「ちょっと気になる社会のこと」に目を向けながら、一市民としての視点や選....
-
04月22日 (火) 更新
米大学卒業式の注目スピーチから得られる学び<イベントレポート>
ニューヨークを拠点に地政学リスク分析の分野でご活躍され、米国社会、日本社会を鋭く分析されているライターの渡邊裕子さんに、アメリカの大学の卒業....
現在募集中のイベント
-
開催日 : 05月19日 (月) 12:30~14:15
ジェラルド・カーティス氏 特別講演「これからの民主主義」
コロンビア大学政治学名誉教授のジェラルド・カーティス氏をお迎えし、トランプ政権の今後の展望と、これからの民主主義の可能性についてご講演いただ....