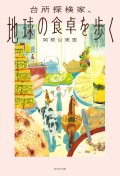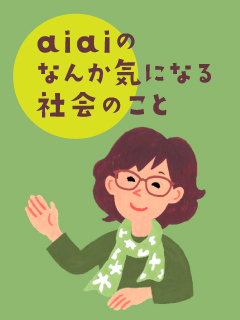記事・レポート
aiaiのなんか気になる社会のこと
【第8回】「コーヒーの一生」から見えてくる風景
更新日 : 2025年02月25日
(火)
【第8回】「コーヒーの一生」から見えてくる風景

朝起きて、何はなくともコーヒー。そんな方も多いのではないでしょうか。日常的にコーヒーを飲むという習慣が広まったのは意外に最近で、20世紀になってからです。エチオピアで500〜600年前から飲まれていたコーヒーは、イエメン、インドネシア経由でヨーロッパに渡り、そこから1本の木がカリブ海のマルティニーク島へ持ち込まれ、それが中南米で育つコーヒーすべての先祖になった—そんなエピソードから始まるドキュメンタリー映画があります。コーヒー好きのCMクリエイター、ブランドン・ローパー自ら製作・監督した作品で、2014年の発表以降世界30カ国108都市で上映会が開催されました。ブルーボトルコーヒーの創業者や全米バリスタチャンピオン、大坊珈琲のオーナーなど、レジェンド級の人々が登場しますが、彼らは主役ではなく、ルワンダやホンジュラスなどのコーヒー農家の生産者の姿を追いつつも、彼らをフィーチャーしているわけでもない。『A Film About Coffee』というタイトルのとおり、主役はコーヒーです。
バイヤーにとってのコーヒーは神秘の豆であり、生産者にとってのコーヒーはただの農産物。それがフラットに対比されています。その異質の関係性がある瞬間つながる場面がありました。バイヤーが生産者たちにエスプレッソをふるまうシーンです。それまで生産者たちは「植えて実を摘んで精製するだけ」で自分たちがどんな種類のコーヒーを育てているか知りませんでした。バリスタが目の前で淹れたエスプレッソを飲み比べ、豆によって異なる風味を自分の舌で感じ取った農夫たちは驚きと誇りの入り混じった何とも言えない表情を浮かべます。続いてカプチーノのシングルとダブルの違いを神妙な顔で確かめます。このささやかな儀式が生産者とバイヤーの関係を一瞬にして変質させたことが映像から伝わってきました。
コーヒーを社会的にとらえると、生産者と購入者の植民地主義的な関係やその是正手段としてのフェアトレード、今後コーヒーブームが加熱することによる環境破壊、気候変動による産地へのダメージといった構造的な問題が浮かび上がります。『A Film About Coffee』でもルワンダのコーヒーはドイツ人の植民者がもちこんだものであるとか、ジェノサイド後に政府がコーヒー産業を支援していることなどが背景として語られますが、そこをことさらに強調することはありません。コーヒーをこよなく愛する人たちがより良質で独特なものを求めて辿り着いたのが特別な豆とその生産者であり、彼らの直接取引が市場を変え、文化を変え、コーヒーのスタンダードを変えました。コーヒーにまつわる構造的な問題を前提とせず、シングルオリジンのコーヒーとそれをつくる人、求める人のネットワークを淡々と細やかに追っていきます。
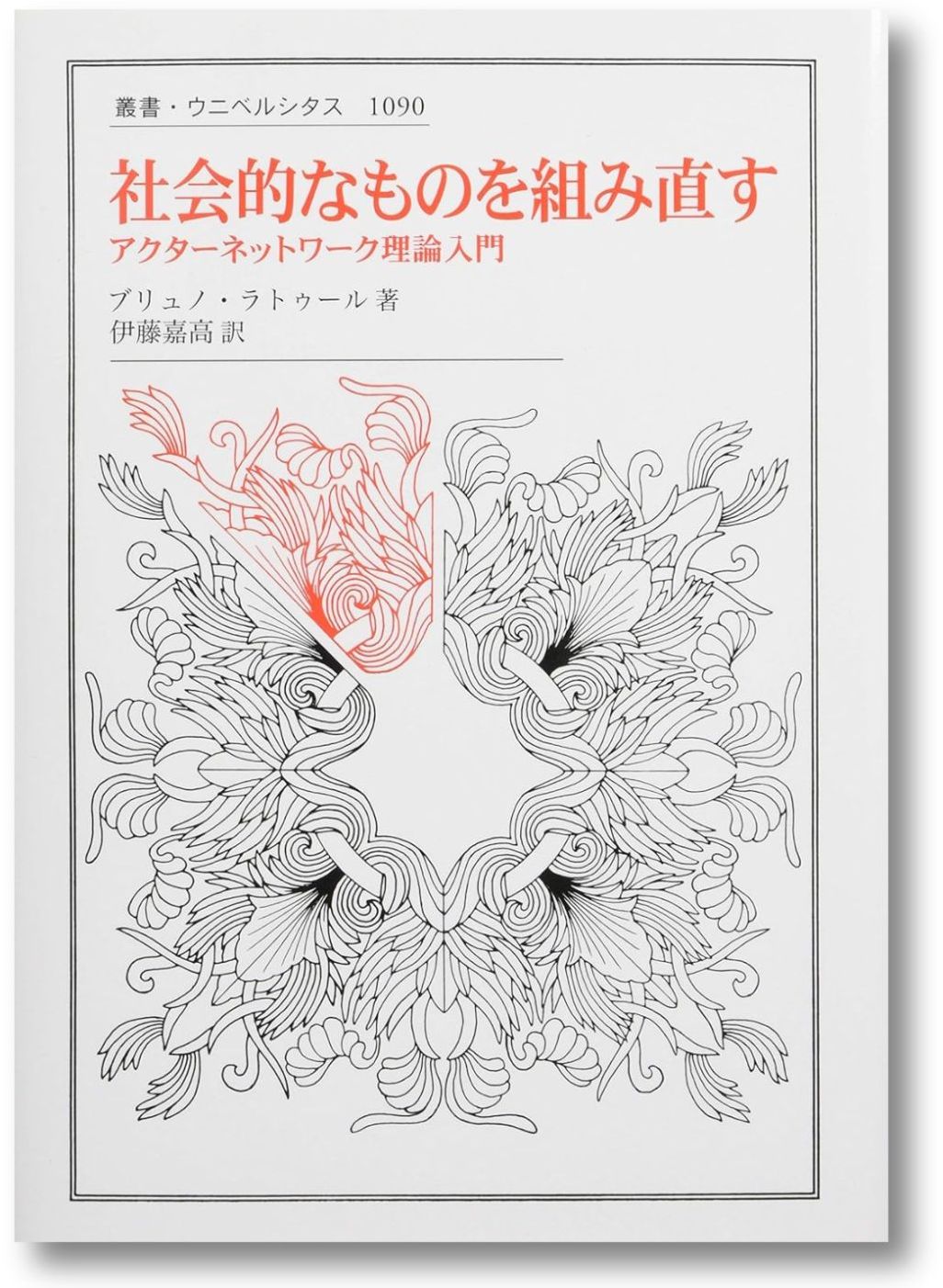
『A Film About Coffee』では、コーヒーの木、コーヒー豆、農夫、発酵槽、生豆袋、貿易会社、バイヤー、ロースター、ペーパーフィルター、サイフォン、エスプレッソマシーン、カフェ、客などはすべて同等の重みを持つ存在として描かれ、これらの「アクター」が連関しあうことによって立ち現れてくる「何か」を、見る者は感じ取ります。その「何か」はおそらく受け取る人によって変わってくる。なぜなら映画を見ることによって自分もそのネットワークの一部になるからです。人間と非人間、見る者と見られる者を分けないANTの記述法はどこまでもフラットです。それゆえにまどろっこしく、どっちつかずで、結局何が言いたいのかわからない(何も言ってない)という批判もあります。しかし、こうしたフラットな目線で時間をかけて点と点をつないでいくことでしか見えてこない兆しもあるのではないでしょうか。
早朝の洛北で開店前の喫茶店やカフェをゲーリーさんと一緒にまわっていると、思わぬ出来事がありました。京都最古の花街、上七軒のお茶や通りで、昭和風情の喫茶店からごみ出しに出てきた年配の女性がゲーリーさんの自転車を呼び止めたのです。ゲーリーさんのママチャリのかごには「コーヒーかす回収しています」と大きく書かれています。「コーヒー集めてはんの?」「はい!」「ちょっと待ってて」。女性は店の奥に入って、アイスクリームの入れ物にいっぱいにいれたコーヒーかすを持ってきました。「これな、うちの畑でモグラ除けに使ってたんやけど、子どもらが芋掘りしたあといらんようになったんで持ってってくれる?」。それを聞いたゲーリーさんは大喜び。「わ、いいんですか? ありがとうございます。毎週回っているのでまたきてもいいですか?」「ええよ、ええよ」。ということで、回収先がまた一つ増えました。
「一杯のコーヒーから夢の花咲くこともある」と歌う昭和歌謡がありますが、「いっぱいのコーヒーかすからご縁のつながることもある」というわけです。ジュンコさんからおしえてもらった話ですが、船岡山公園にコーヒーかす回収スポットを設置したところ、ウォーキングのついでにコーヒーかすを出してくれるようになった人もいるそうです。コーヒーかすの再利用が外出のきっかけにもなるなんて誰が想像したでしょう。そこで顔見知りになった人と世間話が始まるかもしれません。mame-ecoにはいま、人づてに聞いたり地元の新聞の記事で活動を知ったりして集まってきた回収ボランティアが5人います。凍てつく冬の朝、自転車に乗って、開店前のカフェや喫茶店からコーヒーかすを引き取って回るという、ふつうの旅であればまずやらない体験から見えてきたもの、それはコーヒーかすというモノを介した地域の新しいつながりでした。
 スターバックスも10年ほど前からコーヒー抽出後の豆かすを肥料や飼料にリサイクルを始め、2030年までに国内全店舗での実施を目指しています。ジュンコさんは大手企業のこうした動きは、自分たちの活動の後押しになると考えていますが、いちばん大事なことは「無理せず楽しく続けること」「あるものでできて、まねしやすいこと」だといいます。循環スロージャーニーのような取り組みに協力者が集まるのは、リアルな体験が次の行動につながるからではないでしょうか。ゲーリーさんとジュンコさんが実現したいのは「コーヒーの豆かすは捨てるもの、という世の中の常識が変わること」。それは時間のかかるプロセスです。地域コミュニティに根差した地道な活動は、コーヒー豆の循環を生活のなかに定着させるネットワークづくりでもあります。
スターバックスも10年ほど前からコーヒー抽出後の豆かすを肥料や飼料にリサイクルを始め、2030年までに国内全店舗での実施を目指しています。ジュンコさんは大手企業のこうした動きは、自分たちの活動の後押しになると考えていますが、いちばん大事なことは「無理せず楽しく続けること」「あるものでできて、まねしやすいこと」だといいます。循環スロージャーニーのような取り組みに協力者が集まるのは、リアルな体験が次の行動につながるからではないでしょうか。ゲーリーさんとジュンコさんが実現したいのは「コーヒーの豆かすは捨てるもの、という世の中の常識が変わること」。それは時間のかかるプロセスです。地域コミュニティに根差した地道な活動は、コーヒー豆の循環を生活のなかに定着させるネットワークづくりでもあります。
京都には歴史ある喫茶店や個性的なカフェが多くあります。それらを巡って映える写真を撮ったりこだわりの味や香りを楽しむのも素敵ですが、開店前のお店をまわってひたすらコーヒーの豆かすを回収するという、徹底的に映えないツアーは新たな発見に満ちています。コーヒーは一滴も飲みませんでしたが、豆かすを肥料にして育った野菜がたっぷり入ったカレーを美味しくいただきました。毎日何杯もコーヒー飲むという人でも、ほとんどは焙煎された豆から抽出された液体になるまでの「最終商品」としてのコーヒーの姿しか見たことがないでしょう。私もそうでした。一杯のコーヒーの後先に思いを馳せると、コーヒーにまつわる人やモノ、場所や記憶が織りなす思いもよらない風景が見えてきます。
執筆者:中嶋 愛
編集者。ビジネス系出版社で雑誌、単行本、ウェブコンテンツの編集に携わったのち、ソーシャルイノベーションの専門誌、Stanford Social Innovation Reviewの日本版立ち上げに参画。「スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版」創刊編集長。スタンフォード大学修士修了。同志社大学客員教授。庭と建築巡りが好きです。
バイヤーにとってのコーヒーは神秘の豆であり、生産者にとってのコーヒーはただの農産物。それがフラットに対比されています。その異質の関係性がある瞬間つながる場面がありました。バイヤーが生産者たちにエスプレッソをふるまうシーンです。それまで生産者たちは「植えて実を摘んで精製するだけ」で自分たちがどんな種類のコーヒーを育てているか知りませんでした。バリスタが目の前で淹れたエスプレッソを飲み比べ、豆によって異なる風味を自分の舌で感じ取った農夫たちは驚きと誇りの入り混じった何とも言えない表情を浮かべます。続いてカプチーノのシングルとダブルの違いを神妙な顔で確かめます。このささやかな儀式が生産者とバイヤーの関係を一瞬にして変質させたことが映像から伝わってきました。
コーヒーを社会的にとらえると、生産者と購入者の植民地主義的な関係やその是正手段としてのフェアトレード、今後コーヒーブームが加熱することによる環境破壊、気候変動による産地へのダメージといった構造的な問題が浮かび上がります。『A Film About Coffee』でもルワンダのコーヒーはドイツ人の植民者がもちこんだものであるとか、ジェノサイド後に政府がコーヒー産業を支援していることなどが背景として語られますが、そこをことさらに強調することはありません。コーヒーをこよなく愛する人たちがより良質で独特なものを求めて辿り着いたのが特別な豆とその生産者であり、彼らの直接取引が市場を変え、文化を変え、コーヒーのスタンダードを変えました。コーヒーにまつわる構造的な問題を前提とせず、シングルオリジンのコーヒーとそれをつくる人、求める人のネットワークを淡々と細やかに追っていきます。
人間も非人間も含めた連関から見えてくるもの
アクターネットワークセオリー(ANT)という世界の見方があります。社会的現象を、人間と人間以外の存在も含んだアクターの相互作用によって生成されるネットワークとしてとらえるというアプローチです。近代における代表的な世界の理解の方法としては、観察、実験、理論によって真理を突き止めるという科学的アプローチと、真実や事実とされているものを疑いその背後にある構造を解き明かそうとする構築論的アプローチがありますが、いずれも主語は「人間」です。人が真理を発見し、構造を見抜く。アクターネットワークセオリーの主語は人間も非人間も含めた、他の存在に影響を及ぼす能力をもつすべての存在(アクター)です。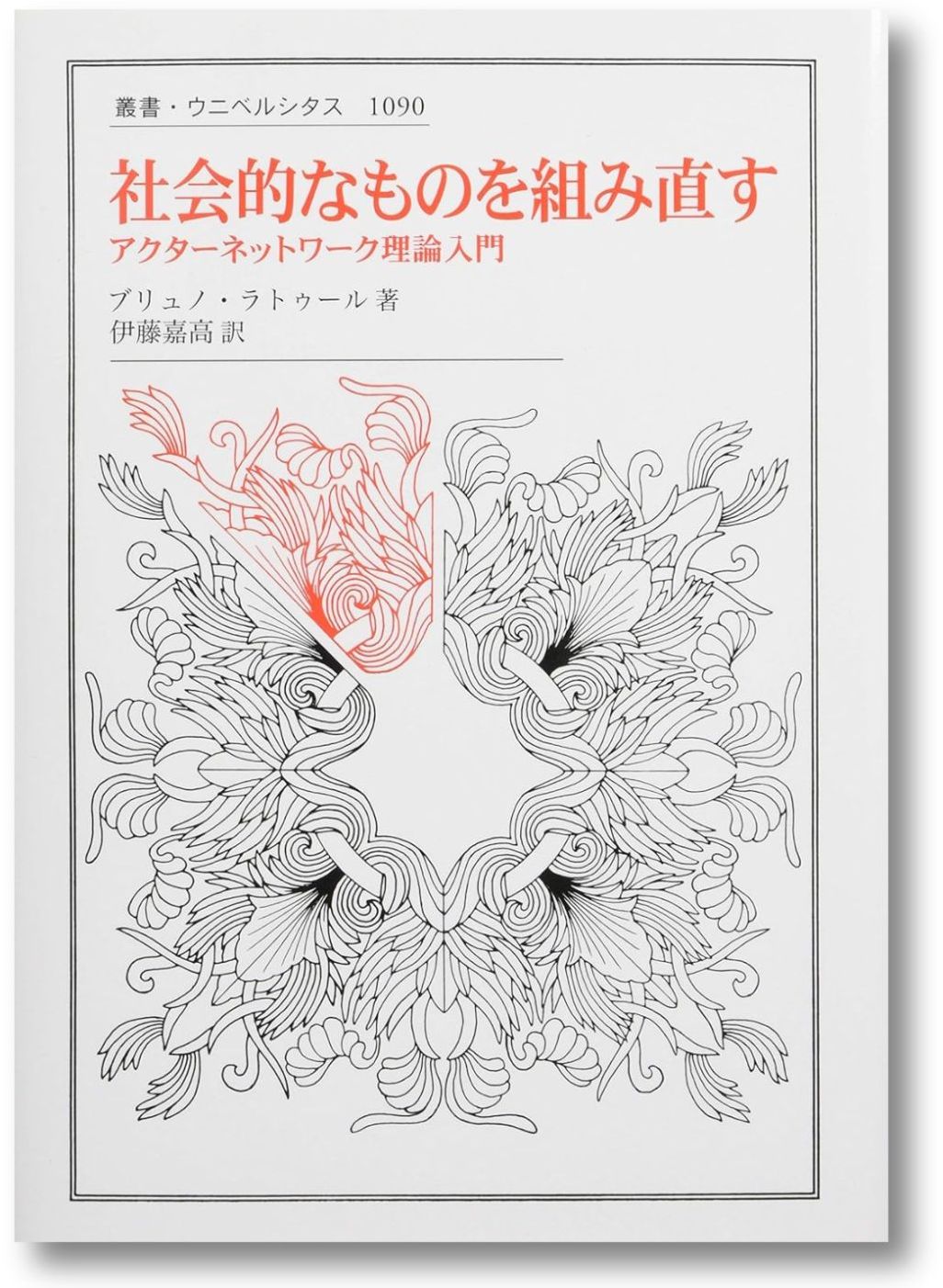
『A Film About Coffee』では、コーヒーの木、コーヒー豆、農夫、発酵槽、生豆袋、貿易会社、バイヤー、ロースター、ペーパーフィルター、サイフォン、エスプレッソマシーン、カフェ、客などはすべて同等の重みを持つ存在として描かれ、これらの「アクター」が連関しあうことによって立ち現れてくる「何か」を、見る者は感じ取ります。その「何か」はおそらく受け取る人によって変わってくる。なぜなら映画を見ることによって自分もそのネットワークの一部になるからです。人間と非人間、見る者と見られる者を分けないANTの記述法はどこまでもフラットです。それゆえにまどろっこしく、どっちつかずで、結局何が言いたいのかわからない(何も言ってない)という批判もあります。しかし、こうしたフラットな目線で時間をかけて点と点をつないでいくことでしか見えてこない兆しもあるのではないでしょうか。
コーヒーの豆かすが織りなすネットワーク
コーヒーの話に戻りましょう。ここからは映画ではなく実体験の話です。昨年12月、京都で「循環スロージャーニー」という企画に参加しました。その一環で、京都のカフェや喫茶店からコーヒーの豆かすを回収する活動を体験しました。この活動を始めたのは、ゲーリー・ブルームさんと妻のジュンコさん。2020年5月から始めた「京都コーヒーかす再利用プロジェクト」mame-ecoでは、これまでに68トンのコーヒーの豆かすを回収しました。これはアフリカ象10頭分くらいの重さになるそうです。二人がコーヒーの豆かすの回収をはじめたきっかけは、コーヒーは収穫した豆の2%しか使われず、あとはゴミとして捨てられてしまうと知ったことからでした。なんとか「土壌に返す」というかたちで再利用できないかと考え、地域密着型掲示板サービス「ジモティー」で豆かすを受け取ってくれる農家を探しました。最初に手を挙げてくれたのは亀岡の王子楽遊農園です。現在は、京都市内55カ所のホテル、レストラン、カフェ、学校などからコーヒーかすを回収し、4件の農家に届けています。使い方もそれぞれです。お米、きのこ、お茶などを栽培する肥料に使っているところもあれば、雑草除けや虫除けに使っているところもあります(コーヒーの豆かすはそのまま使うと植物の生育を抑制する働きがあるので、肥料にする場合は米ぬかやおからなどとまぜる必要があるそうです)。早朝の洛北で開店前の喫茶店やカフェをゲーリーさんと一緒にまわっていると、思わぬ出来事がありました。京都最古の花街、上七軒のお茶や通りで、昭和風情の喫茶店からごみ出しに出てきた年配の女性がゲーリーさんの自転車を呼び止めたのです。ゲーリーさんのママチャリのかごには「コーヒーかす回収しています」と大きく書かれています。「コーヒー集めてはんの?」「はい!」「ちょっと待ってて」。女性は店の奥に入って、アイスクリームの入れ物にいっぱいにいれたコーヒーかすを持ってきました。「これな、うちの畑でモグラ除けに使ってたんやけど、子どもらが芋掘りしたあといらんようになったんで持ってってくれる?」。それを聞いたゲーリーさんは大喜び。「わ、いいんですか? ありがとうございます。毎週回っているのでまたきてもいいですか?」「ええよ、ええよ」。ということで、回収先がまた一つ増えました。
「一杯のコーヒーから夢の花咲くこともある」と歌う昭和歌謡がありますが、「いっぱいのコーヒーかすからご縁のつながることもある」というわけです。ジュンコさんからおしえてもらった話ですが、船岡山公園にコーヒーかす回収スポットを設置したところ、ウォーキングのついでにコーヒーかすを出してくれるようになった人もいるそうです。コーヒーかすの再利用が外出のきっかけにもなるなんて誰が想像したでしょう。そこで顔見知りになった人と世間話が始まるかもしれません。mame-ecoにはいま、人づてに聞いたり地元の新聞の記事で活動を知ったりして集まってきた回収ボランティアが5人います。凍てつく冬の朝、自転車に乗って、開店前のカフェや喫茶店からコーヒーかすを引き取って回るという、ふつうの旅であればまずやらない体験から見えてきたもの、それはコーヒーかすというモノを介した地域の新しいつながりでした。

(写真1)開店前のカフェの店先に置かれているコーヒー豆かす回収用バケツ
(写真2)ゲーリーさんが持参のバケツに回収したコーヒーの豆かすを入れていく
(写真3)上七軒の喫茶店があたらしいコーヒー豆かす回収先になった瞬間
(写真4)mame-ecoには「小さい活動でもいつか大きな変化のカタチとなっていけば」
と願う思いがこめられている
(写真2)ゲーリーさんが持参のバケツに回収したコーヒーの豆かすを入れていく
(写真3)上七軒の喫茶店があたらしいコーヒー豆かす回収先になった瞬間
(写真4)mame-ecoには「小さい活動でもいつか大きな変化のカタチとなっていけば」
と願う思いがこめられている
京都には歴史ある喫茶店や個性的なカフェが多くあります。それらを巡って映える写真を撮ったりこだわりの味や香りを楽しむのも素敵ですが、開店前のお店をまわってひたすらコーヒーの豆かすを回収するという、徹底的に映えないツアーは新たな発見に満ちています。コーヒーは一滴も飲みませんでしたが、豆かすを肥料にして育った野菜がたっぷり入ったカレーを美味しくいただきました。毎日何杯もコーヒー飲むという人でも、ほとんどは焙煎された豆から抽出された液体になるまでの「最終商品」としてのコーヒーの姿しか見たことがないでしょう。私もそうでした。一杯のコーヒーの後先に思いを馳せると、コーヒーにまつわる人やモノ、場所や記憶が織りなす思いもよらない風景が見えてきます。
執筆者:中嶋 愛
編集者。ビジネス系出版社で雑誌、単行本、ウェブコンテンツの編集に携わったのち、ソーシャルイノベーションの専門誌、Stanford Social Innovation Reviewの日本版立ち上げに参画。「スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版」創刊編集長。スタンフォード大学修士修了。同志社大学客員教授。庭と建築巡りが好きです。
参考文献
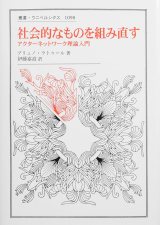
社会的なものを組み直す: アクターネットワーク理論入門
ブリュノ ラトゥール (著), 伊藤 嘉高 (翻訳)法政大学出版局
aiaiのなんか気になる社会のこと インデックス
-
【第1回】ドラッカー曰く「世界最古のNPOは日本のお寺?!」
2024年07月23日 (火)
-
【第2回】「コンヴィヴィアリティ」の視点で、厳しい暑さを乗り切るには?
2024年08月21日 (水)
-
【第3回】美術館は誰のもの?「正の外部性」から考えてみる
2024年09月24日 (火)
-
【第4回】「15分都市」という選択 住み心地のいい街の条件とは?
2024年10月22日 (火)
-
【第5回】私たちは「コモングッド」を取り戻せるか
2024年11月20日 (水)
-
【第6回】世の中は「虚構」で成り立っているという衝撃
2024年12月24日 (火)
-
【第7回】政治の話は嫌いですか ~ポリティカルイノベーション事始め~
2025年01月21日 (火)
-
【第8回】「コーヒーの一生」から見えてくる風景
2025年02月25日 (火)
-
【第9回】なぜ日本の学校では子どもたちが掃除をするのか
2025年03月25日 (火)
注目の記事
-
03月25日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年3月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の"いま"が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
03月25日 (火) 更新
aiaiのなんか気になる社会のこと
「aiaiのなんか気になる社会のこと」は、「社会課題」よりもっと手前の「ちょっと気になる社会のこと」に目を向けながら、一市民としての視点や選....
-
03月25日 (火) 更新
米大学卒業式の注目スピーチから得られる学び<イベントレポート>
ニューヨークを拠点に地政学リスク分析の分野でご活躍され、米国社会、日本社会を鋭く分析されているライターの渡邊裕子さんに、アメリカの大学の卒業....
現在募集中のイベント
-
開催日 : 05月19日 (月) 12:30~14:15
ジェラルド・カーティス氏 特別講演「これからの民主主義」
コロンビア大学政治学名誉教授のジェラルド・カーティス氏をお迎えし、トランプ政権の今後の展望と、これからの民主主義の可能性についてご講演いただ....