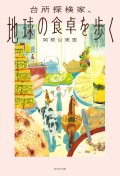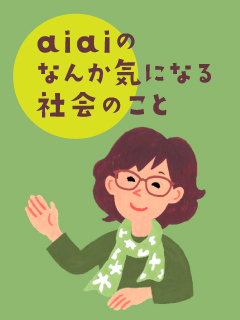記事・レポート
六本木アートカレッジ
<未来を拡張するゲームチェンジャー>イベントレポート
自分だけの視点<EYES>を持つ
更新日 : 2023年07月24日
(月)
【1】小川哲(SF作家)
2023年はChatGPTの出現で、「10年後になくなる仕事は?」といった予想がさらに現実味を増して捉えられています。「人間にとって仕事とは?」「自分らしく生きるとは?」を、より問われる時代となったとも言えるでしょう。
2022-2023年の六本木アートカレッジシリーズ <未来を拡張するゲームチェンジャー U-35>」では、新しい価値を生み出す5名のゲストを招き、トークイベントを開催しました。ゲストに共通していたのは、業界やジャンルの境界にとらわれず、オリジナリティのある道を切り拓いていること。当初「U-35」と年齢で区切っていた企画でしたが、お話を聞くにつれ、彼らが道を切り拓いていく源は「若さ」にあるのではなく、「自分だけの視点<EYES>」にあると感じました。
そこで、<六本木アートカレッジ>でのトークを振り返りながら、ゲストスピーカーの「社会の捉え方」や「世界の見方」など、独自の視点にスポットをあてたイベントレポートをお届けします。
2022-2023年の六本木アートカレッジシリーズ <未来を拡張するゲームチェンジャー U-35>」では、新しい価値を生み出す5名のゲストを招き、トークイベントを開催しました。ゲストに共通していたのは、業界やジャンルの境界にとらわれず、オリジナリティのある道を切り拓いていること。当初「U-35」と年齢で区切っていた企画でしたが、お話を聞くにつれ、彼らが道を切り拓いていく源は「若さ」にあるのではなく、「自分だけの視点<EYES>」にあると感じました。
そこで、<六本木アートカレッジ>でのトークを振り返りながら、ゲストスピーカーの「社会の捉え方」や「世界の見方」など、独自の視点にスポットをあてたイベントレポートをお届けします。
Vol.1 開催日:2022/7/27
SFで世界を解き放つ〜現代に接続する未来のプラグ〜
第1回のゲストスピーカーは、作家の小川哲さん。第168回直木賞を受賞した『地図と拳』(イベント時は受賞前)のお話や、「小説家」という仕事と社会の関係性、過去・現在・未来をどう捉えるか、など、女優で作家の中江有里さんのモデレートでお話いただきました。 SFで世界を解き放つ〜現代に接続する未来のプラグ〜

小川哲's EYES 1過去も未来も、現在とは違う「社会システム・技術レベル・価値観」で生きる人のことを考えるという点は変わらない。
『地図と拳』は第二次世界大戦の満州を舞台にした小説です。僕にとって、第二次世界大戦の戦中や前後で、満州で生活していた人々がどういう価値観でどういうことをしていたかを考えることは、宇宙人について考えるのと一緒だと感じます。どちらも、現代とは違う社会システム、技術レベル、価値観で生きている人々が出てくる話であり、考えるときに使っている筋肉が同じ、という感じがします。硬式テニスと軟式テニスの違いくらいでしょうか。歴史小説の場合は「事実こうだった」という資料はありますが、わからないこともあります。例えば、織田信長の物語を読んだとき、どこで何をした、という事実は存在していても、そこで何を話したか、何を考えたかという、セリフなどは創作です。読者は、かつてあったこととして読んでいるかもしれないですが、資料に残っていないことは推測して書かれています。作家としては、ほとんどSF小説を書いているみたいで、そんなに変わらない。こう言うと歴史小説家に怒られるかもしれないですが(笑)。
小川哲's EYES 2作家は書くときからそう考えているわけではなく、書きながら「気付かされる」。
 『地図と拳』を出版し、書いた動機を聞かれたり、ウクライナとロシアの戦争についてどう思うか、現代日本について、今書く意味は?など聞かれることが多いのですが、実はそこまで考えて書いていません。自分が書きたいことを書いているなかで、現代とつながりはあとからついてきます。SF小説は特にそうで、読者は、未来の架空の設定の話として読むわけです。読むこと自体が快楽だったりもしますが、やはり今自分たちの身に起きていることや、現代社会で起きていること、多くの人が考えていることの延長線上にこの話があるのだと感じさせられないと、感情移入や共感はされない。
『地図と拳』を出版し、書いた動機を聞かれたり、ウクライナとロシアの戦争についてどう思うか、現代日本について、今書く意味は?など聞かれることが多いのですが、実はそこまで考えて書いていません。自分が書きたいことを書いているなかで、現代とつながりはあとからついてきます。SF小説は特にそうで、読者は、未来の架空の設定の話として読むわけです。読むこと自体が快楽だったりもしますが、やはり今自分たちの身に起きていることや、現代社会で起きていること、多くの人が考えていることの延長線上にこの話があるのだと感じさせられないと、感情移入や共感はされない。作家は書くときからそう考えているわけではなく、書きながら気付かされるんですね。架空の話をかいてる自分は、現代に生きて、呼吸をしている実在の人間なので、書いているうちにどうしても現代の要素とリンクしてきます。「なぜ書こうと思ったのか?」と動機を聞かれても「そこに山があった」というか「書いたらおもしろいんじゃないかな」と書いてみて、うまくいくと現代の自分とリンクできたりする、それを知ることが執筆の過程だと思っています。
小川哲's EYES 3「小説家」は責任の所在が明確で、思いついたことを実装できる。
「この登場人物を、次のシーンで殺したいんですが」と上司に言ったら「ダメだ!これは絶対に最後まで生かせ」みたいなことが小説家には無い。
大学ではアラン・チューリングの研究(表象文化論、人文系の研究)をしていて、初期は作家と並行して研究者としてもやっていました。デビュー作で受賞(ハヤカワSFコンテスト大賞)し、2作目も出版出来て仕事がたくさん来たので、この先10年くらいは作家でいけるかなと思い、専業にしました。作家は究極的には1人に耐えられないといけない。孤独を好むくらいでないと厳しいです。デビュー作を書いているときは、大学院生で、アマチュアで、バイトをしながら空いた時間に喫茶店で1人で書いていました。その時に、この書いている作業は、スティーブン・キングも、東野圭吾も同じだ、作家は全員同じことをやっている、と思ったんです。自分の原稿と向き合うのが好きでないとできないと、プロになってからは特に感じます。
今日は体調が悪いから、部下に任せようとかできないですからね。最終的に、責任の所在が明確で、思いついたことを実装できます。例えば「この登場人物を、次のシーンで殺したいんですが」と上司に言ったら「ダメだ!これは絶対に最後まで生かせ」みたいなことが小説家には無い(笑)。

小川哲's EYES 4「作家は、坑道のカナリア」世の中には気づいていないガスが出ているところがあって、まだみんなが有毒だと気づいていないときに、先に<失神>する。
コロナ禍になって、僕自身の「小説を書く」という行為に影響がなくても、読者はコロナと無関係でいられません。パンデミックを作品のなかでどう扱っているかという視点を持ってしまいます。例えば小説の中で、10人くらいで飲んでいるとか、容疑者を密室に集めて探偵が謎解きする描写で、「いや、その前にマスクしろよ」みたいな心理が起こってしまう。カート・ヴォネガットが「作家は、坑道のカナリアだ」と言っています。炭鉱のカナリアは、鉱山で有毒ガスが出ていると先に倒れて、人間がそれを見て逃げる。作家もそれと同じで、世の中には気づいていないガスが出ているところがあって、まだみんなが有毒だと気づいていないときに先に<失神>するのが仕事だということです。コロナのことは考えなければならない問題ですが、それ以外のこと、皆がコロナのせいで見逃してしまっていること、トラブルや、傷ついている人に目を向けたり、逆に10年後に世間がすっかりコロナのことを忘れてしまったときに「忘れちゃだめだ」って言ったり、作家というのはどちらかというとそういう役割があるのかな、と思います。そういうところを見逃さないようにしたい、すくい取りたいと考えたりします。
小川哲's EYES 5世の中の関心事項と全然関係ないことが気になる。例えば「0」や「氷」。それを自分の中にストックしておくと、作品のタネになる。
 今は、インド数学の勉強をしています。これも世の中の議論、関心事項と全然関係ないのですが(笑)。数字の「0」はインドで発見されたとされていて、「0」が生まれたら筆算ができるようになったり、りんごが「0個」と考えられるようになったりしました。漢数字には「0」はないんですよね。だからコロナの感染者数のニュースを見ていても「0」が気になってしまっている自分がいます。小説にできるかどうかは僕次第ですが、今は「0」について考えたい、と思って勉強しています。
今は、インド数学の勉強をしています。これも世の中の議論、関心事項と全然関係ないのですが(笑)。数字の「0」はインドで発見されたとされていて、「0」が生まれたら筆算ができるようになったり、りんごが「0個」と考えられるようになったりしました。漢数字には「0」はないんですよね。だからコロナの感染者数のニュースを見ていても「0」が気になってしまっている自分がいます。小説にできるかどうかは僕次第ですが、今は「0」について考えたい、と思って勉強しています。僕は基本的に気になっていることがたくさんあって、最近だと「氷」も気になっています。冷凍庫がない時代は家に氷がなかったので、冷たい水が飲めなかっただろうとか、氷を初めて見た人はなんて思うのかな?と考えたりします。ガルシア・マルケスの『百年の孤独』という小説の始めに氷が出てきて、それが気になって自分のなかにストックしておくと、日頃見過ごしているものが作品作りのフックになったりします。
他にもマルクス エンゲルスの『資本論』を読んだとき、「え?これは2人の名前なの?」と思ったところから自分の作品『嘘と聖典』に繋がっています。(『嘘と聖典』はマルクスとエンゲルスの出逢いを阻止することで共産主義の消滅を企むCIAを描いた歴史改変SF /第162回直木賞候補作)『地図と拳』については、小学生のとき日本がアメリカと戦争して負けたと知って「絶対負けるのに、なんで戦争したんだろう?」と思い、それでも戦争の道に進んだのはなぜか、というのがずっと心に残っていて、それが作品のタネになっています。
小川哲's EYES 6みんなから遅れを取ること、最短ルートで目的地に向かわないのが小説家の仕事。
「書物」は、作者は1人で、読者はそこに何時間も付き合ってくれます。1人の人間と1対1で長時間対話ができるメディアは他にあまりないと思っています。本を読むことで考え方や、発想が変わる、ひょっとしたら親友と一晩酒飲むくらい深い対話ができる。1000年以上前からあるメディアで、ずっと消えることがない。対話できるメディアとして必要なものだと思います。僕にとっては日常的な考え方ですが、小説は、普通の人が当たり前に通り過ぎている感情だったり出来事だったりをスルーせず、一回立ち止まらないと書けない。みんながさーっと走っていくなかで、「え?これ大丈夫?」と、みんなから遅れを取る、最短ルートで目的地に向かわないのが仕事。いろいろな景色を見せてあげるのが小説の役割でもあるのかな、と思います。あとは、シンプルに自分が書いていて楽しむ、読みたいものを書く。読書好きな1人の人間として、読者としての自分を満足させてあげたいと思っています。
▼トークシリーズ(全5回)詳細はこちら

小川哲さん著書
君のクイズ
小川哲朝日新聞出版
地図と拳
小川哲集英社
嘘と正典
小川哲早川書房

<未来を拡張するゲームチェンジャー U-35>Vol.1
SFで世界を解き放つ〜現代に接続する未来のプラグ〜
『ゲームの王国』で日本SF大賞・山本周五郎賞、『嘘と正典』で直木賞候補となったSF作家・小川哲さんと、自身も作家として活躍する女優・中江有里さんとの対談。作品を生み出す発想力、アイデアの源に迫りながら、「未来」とは何か、社会に伝えていきたいことは何か、などをお話いただきます。
六本木アートカレッジ
<未来を拡張するゲームチェンジャー>イベントレポート インデックス
-
【1】小川哲(SF作家)
2023年07月24日 (月)
-
【2】和田夏実(インタープリター)
2023年08月23日 (水)
-
【3】藤原麻里菜(無駄づくり発明家)
2023年09月26日 (火)
-
【4】細井美裕(サウンドアーティスト)
2023年10月24日 (火)
-
【5】小野澤峻(藝術家)
2023年11月21日 (火)
注目の記事
-
03月25日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年3月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の"いま"が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
03月25日 (火) 更新
aiaiのなんか気になる社会のこと
「aiaiのなんか気になる社会のこと」は、「社会課題」よりもっと手前の「ちょっと気になる社会のこと」に目を向けながら、一市民としての視点や選....
-
03月25日 (火) 更新
米大学卒業式の注目スピーチから得られる学び<イベントレポート>
ニューヨークを拠点に地政学リスク分析の分野でご活躍され、米国社会、日本社会を鋭く分析されているライターの渡邊裕子さんに、アメリカの大学の卒業....
現在募集中のイベント
-
開催日 : 05月19日 (月) 12:30~14:15
ジェラルド・カーティス氏 特別講演「これからの民主主義」
コロンビア大学政治学名誉教授のジェラルド・カーティス氏をお迎えし、トランプ政権の今後の展望と、これからの民主主義の可能性についてご講演いただ....