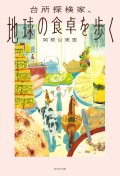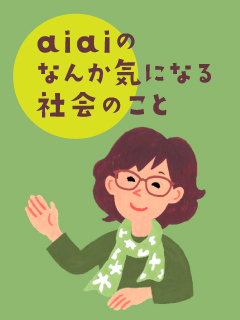記事・レポート
リスキリングは次のフェーズへ!<イベントレポート>
更新日 : 2025年02月25日
(火)
【4章】定年4.0時代のリスキリング

開催日:2024年6月20日 (木) 19:00~20:30 イベント詳細
スピーカー:後藤宗明 (一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ代表理事
SkyHive Technologies 日本代表)
田中若菜 (LinkedIn 日本代表)
柳川範之 (東京大学 大学院経済学研究科・経済学部教授)
定年4.0時代のリスキリング 【質疑応答】
会場:貴重なお話ありがとうございました。柳川先生が最初にお話になった慶應大学のサマースクールのように(第1章)、強く問題意識を持って、単位のためだけではなく自分から学ぶ姿勢を持ってもらうためにはどうすればいいでしょうか。社会経験があれば問題意識もあると思うのですが、逆に若い学生にどうしたらそう思ってもらえるのか、お考えをお聞かせください。
 柳川:後藤さんがおっしゃていた、二つ以上の異なる分野の知識を統合する「学際的スキル」(第3章)はとても大事になってきています。ただ、単に色々な分野の知識を学べば学際的な能力になるか、というとそうではなく、田中さんがお話されたように、こんな仕事に就きたいとか、こんなスキルを身につけたい、そういった目的意識があるから、色々な分野の知識が自分の頭の中で融合するのだと思います。質問に対する僕の答えは、やはり学校を卒業した後、問題意識を持ったとき、もう1回学びたいと思った人が学びに来ればいいと思います。僕のゼミの生徒が卒業をする時には、会社の中にいて何か足りないと思ったり、もっと学んでおけばよかったと思ったりしたときが、学ぶのに一番いい時だから、戻ってきて躊躇なく知識を身につけたらいい、いつでも待っているから、と伝えるようにしています。やはり、ある程度社会経験を積んだことによって初めて出てくる問題意識や学ぶ力というのはあると思います。そういうものを大事にすることが、狭い意味でのリスキリングではなく、拡大解釈された「学び直し」も含めた意味でのリスキリングではないかと思います。
柳川:後藤さんがおっしゃていた、二つ以上の異なる分野の知識を統合する「学際的スキル」(第3章)はとても大事になってきています。ただ、単に色々な分野の知識を学べば学際的な能力になるか、というとそうではなく、田中さんがお話されたように、こんな仕事に就きたいとか、こんなスキルを身につけたい、そういった目的意識があるから、色々な分野の知識が自分の頭の中で融合するのだと思います。質問に対する僕の答えは、やはり学校を卒業した後、問題意識を持ったとき、もう1回学びたいと思った人が学びに来ればいいと思います。僕のゼミの生徒が卒業をする時には、会社の中にいて何か足りないと思ったり、もっと学んでおけばよかったと思ったりしたときが、学ぶのに一番いい時だから、戻ってきて躊躇なく知識を身につけたらいい、いつでも待っているから、と伝えるようにしています。やはり、ある程度社会経験を積んだことによって初めて出てくる問題意識や学ぶ力というのはあると思います。そういうものを大事にすることが、狭い意味でのリスキリングではなく、拡大解釈された「学び直し」も含めた意味でのリスキリングではないかと思います。
会場:お世話になった上司が続々と定年を迎えて、すごく優秀な方なのにやることがないと聞いたりすると、ちょっと寂しいなと思ったりしています。これからそういった世代のボリュームが増えていくと思うので、人生後半戦のリスキリングをどのようにしたらいいかお伺いしたいです。
 田中:同じようなお悩みをたくさんの経営者から私も日々聞いております。その方々がスキルの棚卸をすると、皆さんものすごいスキルをお持ちなので、まずそれを可視化できたらと思います。シンガポールの事例ですが、シンガポール政府は2024年の初めから55歳以上の国民全員に無料でLinkedIn Learningを提供しています。AI人材を増やして国力を上げる、という戦略をまさに実行しているわけです。そこに至るまでの経緯は、ちょうど2年ぐらい前にシンガポールの官僚にLinkedIn Learningが導入されると、1年間でスキルアップしたAI人材が本当に増えました。そのデータをもとに、国としての戦略を練るようになったということです。シンガポールの5年後、10年後はかなり楽しみです。日本でも同じような取り組みをすると、データに基づいて色々見えてきて面白いのではないかなと思います。
田中:同じようなお悩みをたくさんの経営者から私も日々聞いております。その方々がスキルの棚卸をすると、皆さんものすごいスキルをお持ちなので、まずそれを可視化できたらと思います。シンガポールの事例ですが、シンガポール政府は2024年の初めから55歳以上の国民全員に無料でLinkedIn Learningを提供しています。AI人材を増やして国力を上げる、という戦略をまさに実行しているわけです。そこに至るまでの経緯は、ちょうど2年ぐらい前にシンガポールの官僚にLinkedIn Learningが導入されると、1年間でスキルアップしたAI人材が本当に増えました。そのデータをもとに、国としての戦略を練るようになったということです。シンガポールの5年後、10年後はかなり楽しみです。日本でも同じような取り組みをすると、データに基づいて色々見えてきて面白いのではないかなと思います。
 後藤:このタイミングで、素晴らしいご質問を頂戴していただきありがとうございます。というもの、僕は8月に「定年4.0時代のリスキリング」について書いた書籍『中高年リスキリング これからも必要とされる働き方を手にいれる』を出版します(2024年8月9日出版)。質問者の方、仕込みじゃないですよね?(笑)。
後藤:このタイミングで、素晴らしいご質問を頂戴していただきありがとうございます。というもの、僕は8月に「定年4.0時代のリスキリング」について書いた書籍『中高年リスキリング これからも必要とされる働き方を手にいれる』を出版します(2024年8月9日出版)。質問者の方、仕込みじゃないですよね?(笑)。
僕の今の問題意識もまさにそこにあります。早期退職、役職定年、定年による再雇用によって、優秀な方々が給与が減っていくこと、それからポジションを外されることによって精神的に落ち込んでしまう、というのは本当に日本の財産の流出、消失だと思います。これをどうしたらいいのかを、ずっと考えているなかで「定年4.0時代」という定義をしました。そもそも「定年3.0時代」というのは、経済コラムニストの大江英樹さんが定義をされた概念で、人生100年時代、お金・健康・孤独の三つを誰もが考えなければならなくなった時代、という定義でした。これは生成AI前の定義でしたので、生成AIが出た後に、大きくこの定年の形が変わると考え、僕は「定年4.0時代」を、「リスキリングで現在の雇用に頼らない人生とキャリアを自ら創造する時代」と定義しました。
日本は少子高齢化も進んでいきますので、シニア世代の方に頼っていくことが必要です。ただ、人手不足のためにシニアの方がどんどん仕事につけると予測をされてる方もいらっしゃるのですが、僕はそうならないと思っています。その理由の一つ目は、とにかくAIロボットの進化が激しいので、自動化が急速に進んだ中で若い方たちから仕事のアサインがされると、高齢者のポジションは後回しになります。二つ目は、政策が変わってグローバルな人材を入れるとなったときには、やはりシニア世代の雇用の優先順位が下がります。三つ目は、すごく難しいことだと思うのですが、やはり若い方が上の年齢の方を扱いづらいという意識は、どうしても残ると思います。そのシニアバイアスを変えていくのには時間がかかります。田中さんが例に挙げたシンガポールも、少子高齢化の中で先手を打って、高齢者の方々にリスキリングをしているわけですが、日本は定年=上がりというイメージがあって、もう新しいことをやりたくない、やらなくてもいいという固定観念もありますよね。そこで提言したいのは、この先色々な専門性を持った方が定年をされていくので、専門性×デジタルスキル、専門性×グリーンスキルといった形でかけあわせて、新しく自分のスキルを創造していくことです。そして会社、雇用に捉われず、個人事業主、フリーランスという形で、自分で自分のポジションを確保していく、そういった働き方がこれからの時代に求められていくのではないかと思っています。さらに詳しくは、僕の新刊を読んでいただければ、ということでございます(笑)。
会場:金融機関に勤めており、自治体や企業の方とお話する中で、リスキリングがスタートアップ、イノベーションを推進していく部分もある一方で、地元の企業がどんどん後継者不足で廃業というようなお話もあります。リスキリングを、行政や経済団体などと一緒に取り組んでいく、大きな枠組みを作っていく、そういうことに対して考えられていること、取り組まれていることがあるのでしょうか。
後藤:はい、こちらもまさに今、取り組みを始めています。地方自治体の皆さんとその地域の成長産業を支えていくためのリスキリングで、大学を巻き込んだり、あるいはその地域の中核となっている地方銀行さんに一緒に入っていただく取り組みがあります。リスキリングをすることによって、例えばロボットを導入するとなったときに、大きな設備投資、資金が必要になることがあります。そのときに地域の金融機関が実際にそこをサポートしながら、リスキリングを後押しするような産学官連携の仕組みづくりを、20自治体ぐらいでやっています。実は、後継者問題もリスキリングが重要で、ある意味、後継者がいる会社はリスキリングが進みやすいですね。ただ、残念ながら後継者がいない会社の社長さんは、自分の代で終えるつもりなのでリスキリングなんかやっても無駄だとおっしゃられたりします。そこで、いやいやせっかくなので事業継続をしてくださいと、後継者探しをお手伝いしたりすることもあります。
また、今日はメイントピックスではなかったので詳しくお話をしませんでしたが、スタートアップからも学ぶことはたくさんあります。デジタル化が進んでない会社で、いきなりOJTでAIを勉強できるかというと、そもそも専門家が中にいないとできないですよね。そこで「アプレンティスシップ制度」と言うのですが、まずAIのプロジェクトを作って、AIのスタートアップと一緒にそのプロジェクトをやることで、一緒に仕事をすることそのものがリスキリングになっていくというものです。そういった仕組みづくりも、ある自治体と一緒にやっています。
柳川:後藤さん、田中さん、ありがとうございました。AIが出てきたり、スタートアップが出てきたりすることによって産業構造も含め、いろいろなものが変わってきていると思います。だから国も企業も、今までと同じようにはできないし、方向転換をしていかなければいけない。世の中全体が大きくやるべきことを変えていく中で、新しいチャレンジをしていく個人ベースのリスキリング、取り組みがすごく大事だということが確認できたと思います。いろいろなお立場の方がいらっしゃると思いますが、ご参考になれば幸いです。ありがとうございました。

(左から)後藤宗明さん、田中若菜さん、柳川範之さん
 柳川:後藤さんがおっしゃていた、二つ以上の異なる分野の知識を統合する「学際的スキル」(第3章)はとても大事になってきています。ただ、単に色々な分野の知識を学べば学際的な能力になるか、というとそうではなく、田中さんがお話されたように、こんな仕事に就きたいとか、こんなスキルを身につけたい、そういった目的意識があるから、色々な分野の知識が自分の頭の中で融合するのだと思います。質問に対する僕の答えは、やはり学校を卒業した後、問題意識を持ったとき、もう1回学びたいと思った人が学びに来ればいいと思います。僕のゼミの生徒が卒業をする時には、会社の中にいて何か足りないと思ったり、もっと学んでおけばよかったと思ったりしたときが、学ぶのに一番いい時だから、戻ってきて躊躇なく知識を身につけたらいい、いつでも待っているから、と伝えるようにしています。やはり、ある程度社会経験を積んだことによって初めて出てくる問題意識や学ぶ力というのはあると思います。そういうものを大事にすることが、狭い意味でのリスキリングではなく、拡大解釈された「学び直し」も含めた意味でのリスキリングではないかと思います。
柳川:後藤さんがおっしゃていた、二つ以上の異なる分野の知識を統合する「学際的スキル」(第3章)はとても大事になってきています。ただ、単に色々な分野の知識を学べば学際的な能力になるか、というとそうではなく、田中さんがお話されたように、こんな仕事に就きたいとか、こんなスキルを身につけたい、そういった目的意識があるから、色々な分野の知識が自分の頭の中で融合するのだと思います。質問に対する僕の答えは、やはり学校を卒業した後、問題意識を持ったとき、もう1回学びたいと思った人が学びに来ればいいと思います。僕のゼミの生徒が卒業をする時には、会社の中にいて何か足りないと思ったり、もっと学んでおけばよかったと思ったりしたときが、学ぶのに一番いい時だから、戻ってきて躊躇なく知識を身につけたらいい、いつでも待っているから、と伝えるようにしています。やはり、ある程度社会経験を積んだことによって初めて出てくる問題意識や学ぶ力というのはあると思います。そういうものを大事にすることが、狭い意味でのリスキリングではなく、拡大解釈された「学び直し」も含めた意味でのリスキリングではないかと思います。 会場:お世話になった上司が続々と定年を迎えて、すごく優秀な方なのにやることがないと聞いたりすると、ちょっと寂しいなと思ったりしています。これからそういった世代のボリュームが増えていくと思うので、人生後半戦のリスキリングをどのようにしたらいいかお伺いしたいです。
 田中:同じようなお悩みをたくさんの経営者から私も日々聞いております。その方々がスキルの棚卸をすると、皆さんものすごいスキルをお持ちなので、まずそれを可視化できたらと思います。シンガポールの事例ですが、シンガポール政府は2024年の初めから55歳以上の国民全員に無料でLinkedIn Learningを提供しています。AI人材を増やして国力を上げる、という戦略をまさに実行しているわけです。そこに至るまでの経緯は、ちょうど2年ぐらい前にシンガポールの官僚にLinkedIn Learningが導入されると、1年間でスキルアップしたAI人材が本当に増えました。そのデータをもとに、国としての戦略を練るようになったということです。シンガポールの5年後、10年後はかなり楽しみです。日本でも同じような取り組みをすると、データに基づいて色々見えてきて面白いのではないかなと思います。
田中:同じようなお悩みをたくさんの経営者から私も日々聞いております。その方々がスキルの棚卸をすると、皆さんものすごいスキルをお持ちなので、まずそれを可視化できたらと思います。シンガポールの事例ですが、シンガポール政府は2024年の初めから55歳以上の国民全員に無料でLinkedIn Learningを提供しています。AI人材を増やして国力を上げる、という戦略をまさに実行しているわけです。そこに至るまでの経緯は、ちょうど2年ぐらい前にシンガポールの官僚にLinkedIn Learningが導入されると、1年間でスキルアップしたAI人材が本当に増えました。そのデータをもとに、国としての戦略を練るようになったということです。シンガポールの5年後、10年後はかなり楽しみです。日本でも同じような取り組みをすると、データに基づいて色々見えてきて面白いのではないかなと思います。 後藤:このタイミングで、素晴らしいご質問を頂戴していただきありがとうございます。というもの、僕は8月に「定年4.0時代のリスキリング」について書いた書籍『中高年リスキリング これからも必要とされる働き方を手にいれる』を出版します(2024年8月9日出版)。質問者の方、仕込みじゃないですよね?(笑)。
後藤:このタイミングで、素晴らしいご質問を頂戴していただきありがとうございます。というもの、僕は8月に「定年4.0時代のリスキリング」について書いた書籍『中高年リスキリング これからも必要とされる働き方を手にいれる』を出版します(2024年8月9日出版)。質問者の方、仕込みじゃないですよね?(笑)。僕の今の問題意識もまさにそこにあります。早期退職、役職定年、定年による再雇用によって、優秀な方々が給与が減っていくこと、それからポジションを外されることによって精神的に落ち込んでしまう、というのは本当に日本の財産の流出、消失だと思います。これをどうしたらいいのかを、ずっと考えているなかで「定年4.0時代」という定義をしました。そもそも「定年3.0時代」というのは、経済コラムニストの大江英樹さんが定義をされた概念で、人生100年時代、お金・健康・孤独の三つを誰もが考えなければならなくなった時代、という定義でした。これは生成AI前の定義でしたので、生成AIが出た後に、大きくこの定年の形が変わると考え、僕は「定年4.0時代」を、「リスキリングで現在の雇用に頼らない人生とキャリアを自ら創造する時代」と定義しました。
日本は少子高齢化も進んでいきますので、シニア世代の方に頼っていくことが必要です。ただ、人手不足のためにシニアの方がどんどん仕事につけると予測をされてる方もいらっしゃるのですが、僕はそうならないと思っています。その理由の一つ目は、とにかくAIロボットの進化が激しいので、自動化が急速に進んだ中で若い方たちから仕事のアサインがされると、高齢者のポジションは後回しになります。二つ目は、政策が変わってグローバルな人材を入れるとなったときには、やはりシニア世代の雇用の優先順位が下がります。三つ目は、すごく難しいことだと思うのですが、やはり若い方が上の年齢の方を扱いづらいという意識は、どうしても残ると思います。そのシニアバイアスを変えていくのには時間がかかります。田中さんが例に挙げたシンガポールも、少子高齢化の中で先手を打って、高齢者の方々にリスキリングをしているわけですが、日本は定年=上がりというイメージがあって、もう新しいことをやりたくない、やらなくてもいいという固定観念もありますよね。そこで提言したいのは、この先色々な専門性を持った方が定年をされていくので、専門性×デジタルスキル、専門性×グリーンスキルといった形でかけあわせて、新しく自分のスキルを創造していくことです。そして会社、雇用に捉われず、個人事業主、フリーランスという形で、自分で自分のポジションを確保していく、そういった働き方がこれからの時代に求められていくのではないかと思っています。さらに詳しくは、僕の新刊を読んでいただければ、ということでございます(笑)。
会場:金融機関に勤めており、自治体や企業の方とお話する中で、リスキリングがスタートアップ、イノベーションを推進していく部分もある一方で、地元の企業がどんどん後継者不足で廃業というようなお話もあります。リスキリングを、行政や経済団体などと一緒に取り組んでいく、大きな枠組みを作っていく、そういうことに対して考えられていること、取り組まれていることがあるのでしょうか。
後藤:はい、こちらもまさに今、取り組みを始めています。地方自治体の皆さんとその地域の成長産業を支えていくためのリスキリングで、大学を巻き込んだり、あるいはその地域の中核となっている地方銀行さんに一緒に入っていただく取り組みがあります。リスキリングをすることによって、例えばロボットを導入するとなったときに、大きな設備投資、資金が必要になることがあります。そのときに地域の金融機関が実際にそこをサポートしながら、リスキリングを後押しするような産学官連携の仕組みづくりを、20自治体ぐらいでやっています。実は、後継者問題もリスキリングが重要で、ある意味、後継者がいる会社はリスキリングが進みやすいですね。ただ、残念ながら後継者がいない会社の社長さんは、自分の代で終えるつもりなのでリスキリングなんかやっても無駄だとおっしゃられたりします。そこで、いやいやせっかくなので事業継続をしてくださいと、後継者探しをお手伝いしたりすることもあります。
また、今日はメイントピックスではなかったので詳しくお話をしませんでしたが、スタートアップからも学ぶことはたくさんあります。デジタル化が進んでない会社で、いきなりOJTでAIを勉強できるかというと、そもそも専門家が中にいないとできないですよね。そこで「アプレンティスシップ制度」と言うのですが、まずAIのプロジェクトを作って、AIのスタートアップと一緒にそのプロジェクトをやることで、一緒に仕事をすることそのものがリスキリングになっていくというものです。そういった仕組みづくりも、ある自治体と一緒にやっています。
柳川:後藤さん、田中さん、ありがとうございました。AIが出てきたり、スタートアップが出てきたりすることによって産業構造も含め、いろいろなものが変わってきていると思います。だから国も企業も、今までと同じようにはできないし、方向転換をしていかなければいけない。世の中全体が大きくやるべきことを変えていく中で、新しいチャレンジをしていく個人ベースのリスキリング、取り組みがすごく大事だということが確認できたと思います。いろいろなお立場の方がいらっしゃると思いますが、ご参考になれば幸いです。ありがとうございました。

(左から)後藤宗明さん、田中若菜さん、柳川範之さん
リスキリングは次のフェーズへ!<イベントレポート> インデックス
-
【1章】自ら学び、キャリアを創造する必要性
2025年01月21日 (火)
-
【2章】リスキリングは日本を救う〜スキルの棚卸しと可視化〜
2025年01月21日 (火)
-
【3章】AI時代に求められる「学際的なスキル」
2025年02月25日 (火)
-
【4章】定年4.0時代のリスキリング
2025年02月25日 (火)
注目の記事
-
03月25日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年3月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の"いま"が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
03月25日 (火) 更新
aiaiのなんか気になる社会のこと
「aiaiのなんか気になる社会のこと」は、「社会課題」よりもっと手前の「ちょっと気になる社会のこと」に目を向けながら、一市民としての視点や選....
-
03月25日 (火) 更新
米大学卒業式の注目スピーチから得られる学び<イベントレポート>
ニューヨークを拠点に地政学リスク分析の分野でご活躍され、米国社会、日本社会を鋭く分析されているライターの渡邊裕子さんに、アメリカの大学の卒業....
現在募集中のイベント
-
開催日 : 05月19日 (月) 12:30~14:15
ジェラルド・カーティス氏 特別講演「これからの民主主義」
コロンビア大学政治学名誉教授のジェラルド・カーティス氏をお迎えし、トランプ政権の今後の展望と、これからの民主主義の可能性についてご講演いただ....