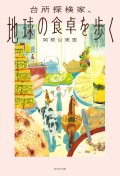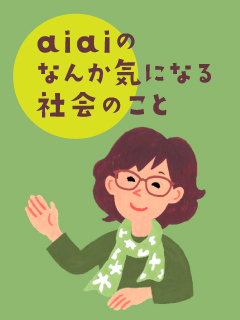本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年2月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の”いま”が見えてくる。
新刊書籍の中から、いま知っておきたい10冊をご紹介します。
今月の10選は、『会社と社会の読書会』、『責任と物語』など。あなたの気になる本は何?
※「本から「いま」が見えてくる新刊10選」をお読みになったご感想など、お気軽にお聞かせください。
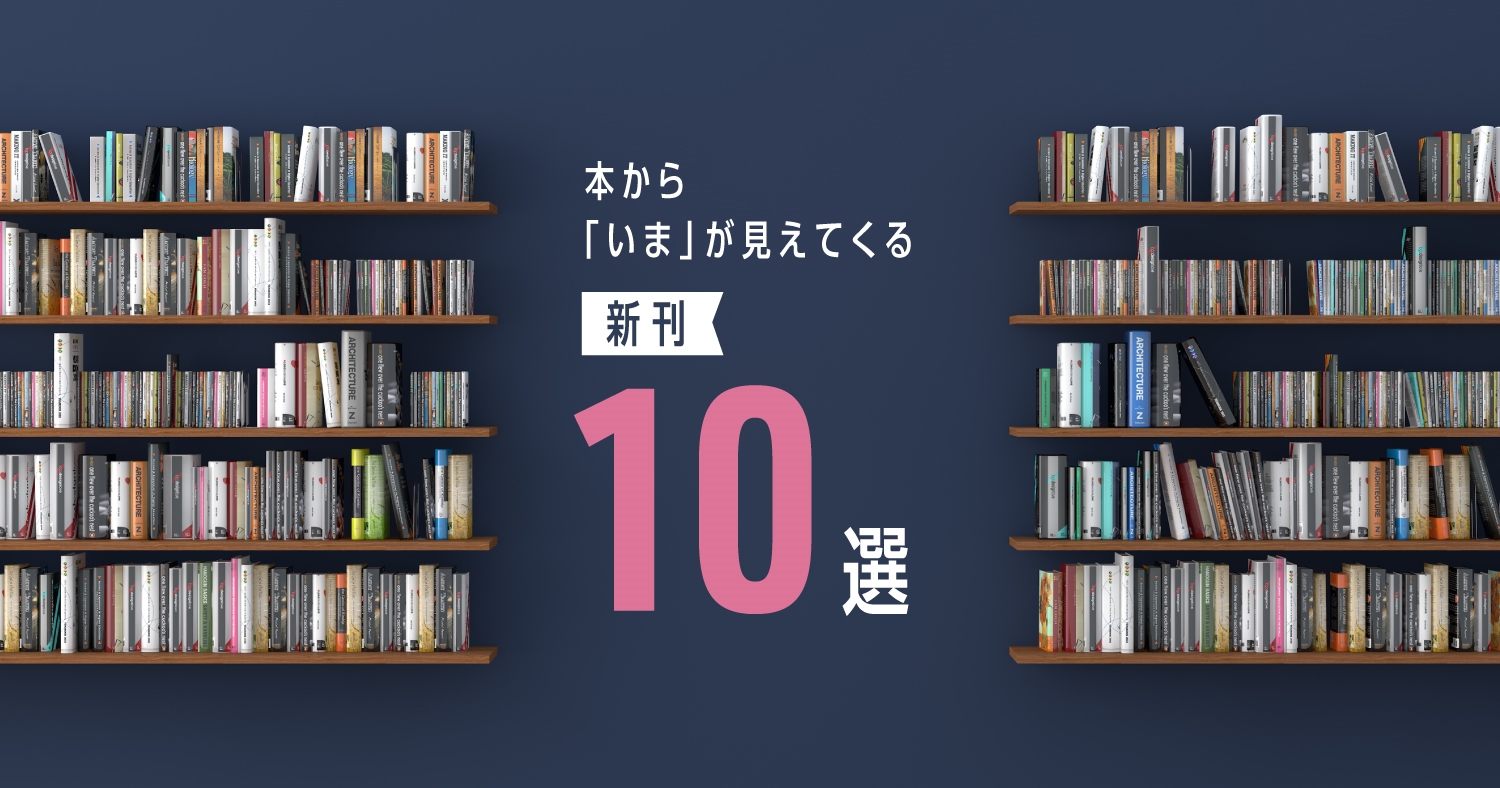
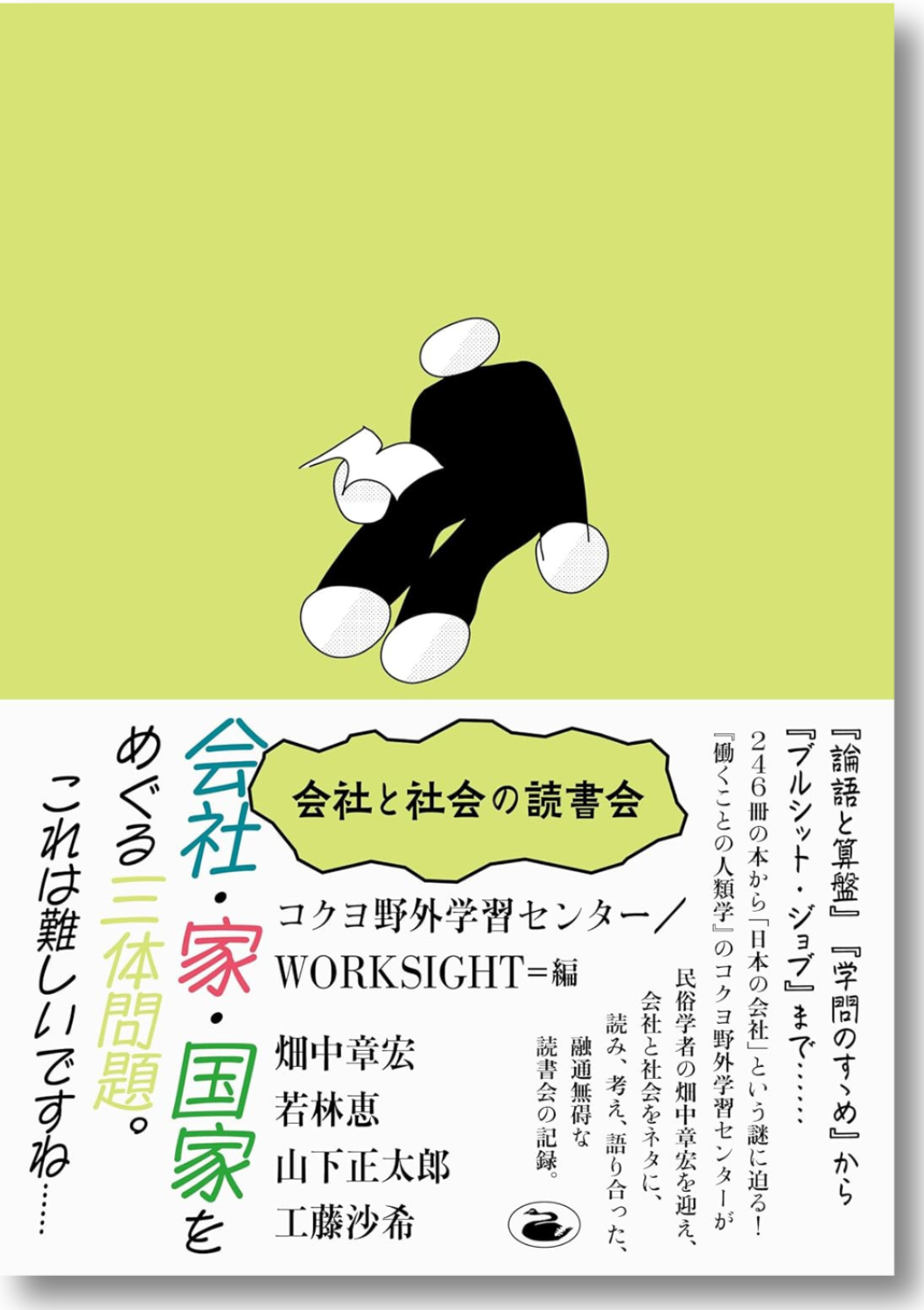
本書は、コクヨワークスタイル研究所とコンテンツレーベル黒鳥社がコラボレーションして展開するリサーチユニット「コクヨ野外学習センター」が、民俗学者の畑中彰宏をゲストに迎えて実施 した読書会での対話を書籍化したもの。「会社」と「社会」のからまりあった関係を、明治期から現代までに刊行された合計246冊の本を参照しながら考察していきます。
会社に入ること、会社で働くことが当たり前ではなくなってきた昨今、「社会に出る」とはどういうことなのか。果たして会社はなんのためにあるのか。会社と社会の捉え方を更新する、”社会人”必読の一冊です。
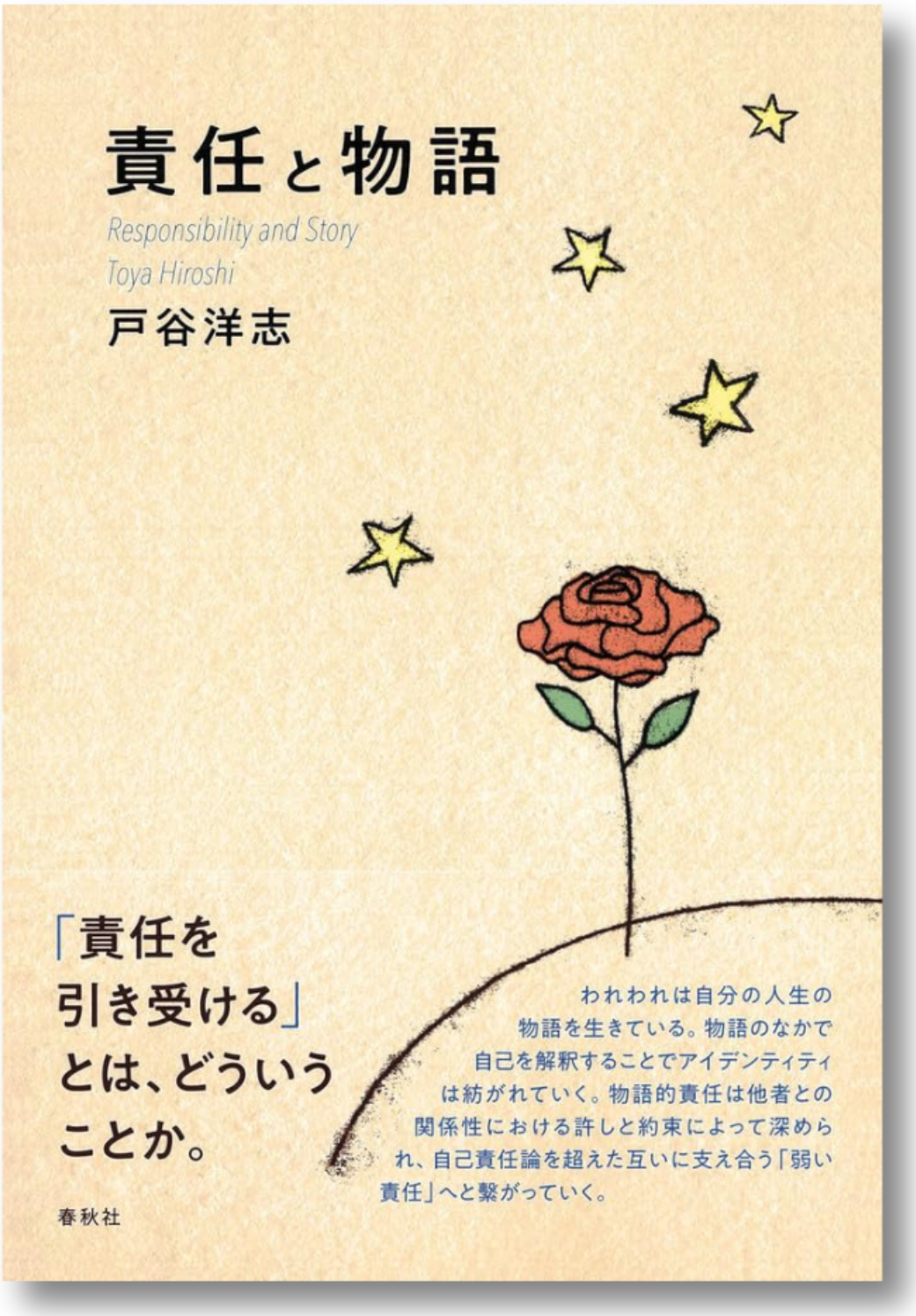
責任と物語
2024年9月の10選でも取り上げた哲学者・戸谷洋志の「責任」をめぐる論考の続編のような本。前著では「弱い責任」という概念で、「自己責任」のように個人に帰されるものとは異なる、社会関係としての責任のあり方を提示しましたが、本書では「自己」と「責任」の関係について改めて考察していきます。「責任を引き受ける」ことについて考えを巡らせることは、社会の中での自分自身の座標を探るようなことかもしれません。
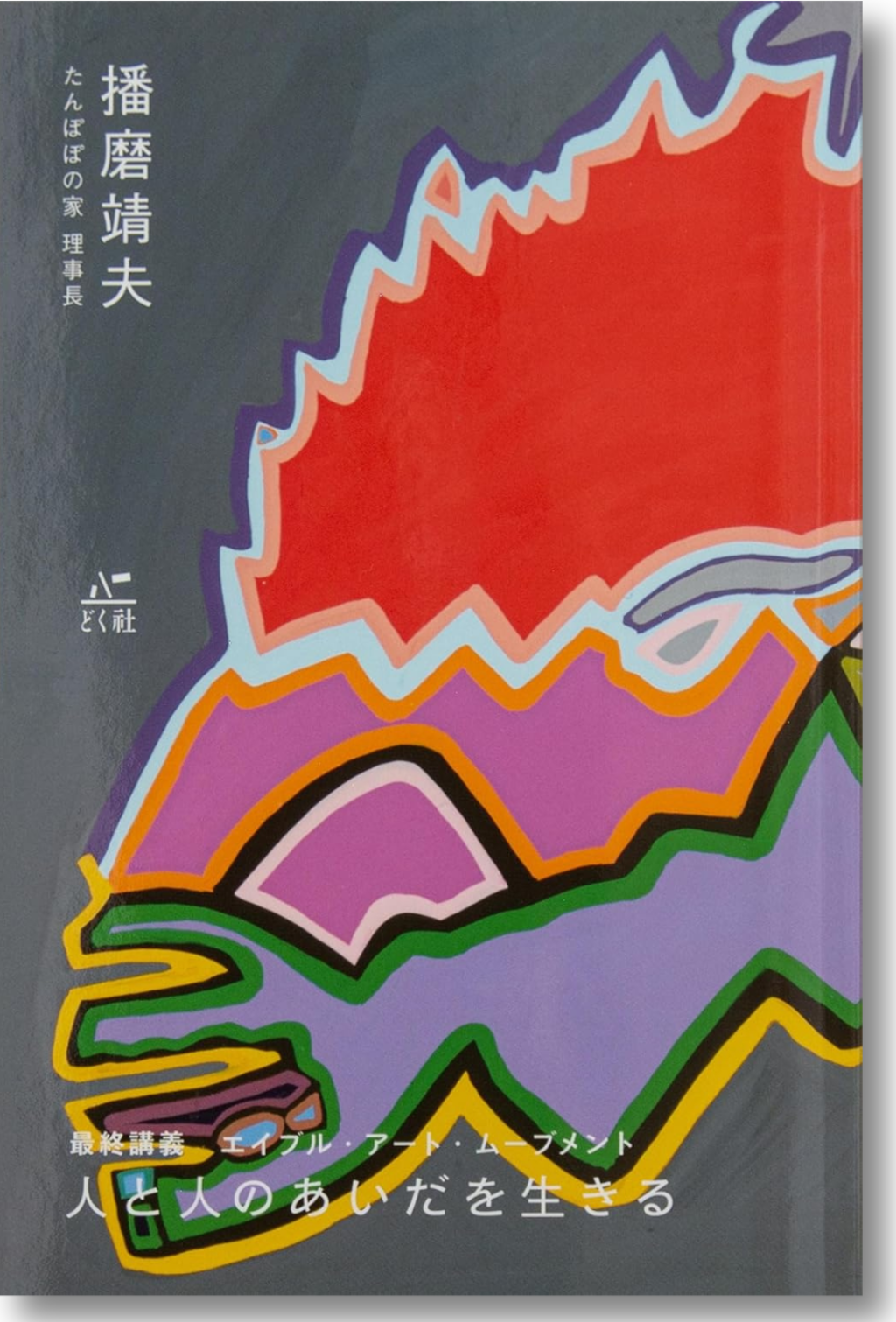
人と人のあいだを生きる
最終講義エイブル・アート・ムーブメント
新聞記者から障害者福祉の世界に転身、市民団体「たんぽぽの家」の理事長を務め、「エイブル・アート・ムーブメント(可能性の芸術運動)」を提唱するなど、50年にわたりアートとケアを結ぶ活動を行い、昨年末に82歳でその生涯を終えた播磨靖夫の言葉を集めた一冊。人が「生きる」ことの根幹を問い続けた播磨の思想と実践は、時代も「アート」や「福祉」といった領域も超えて、今を生きるわたしたちの心に響きます。
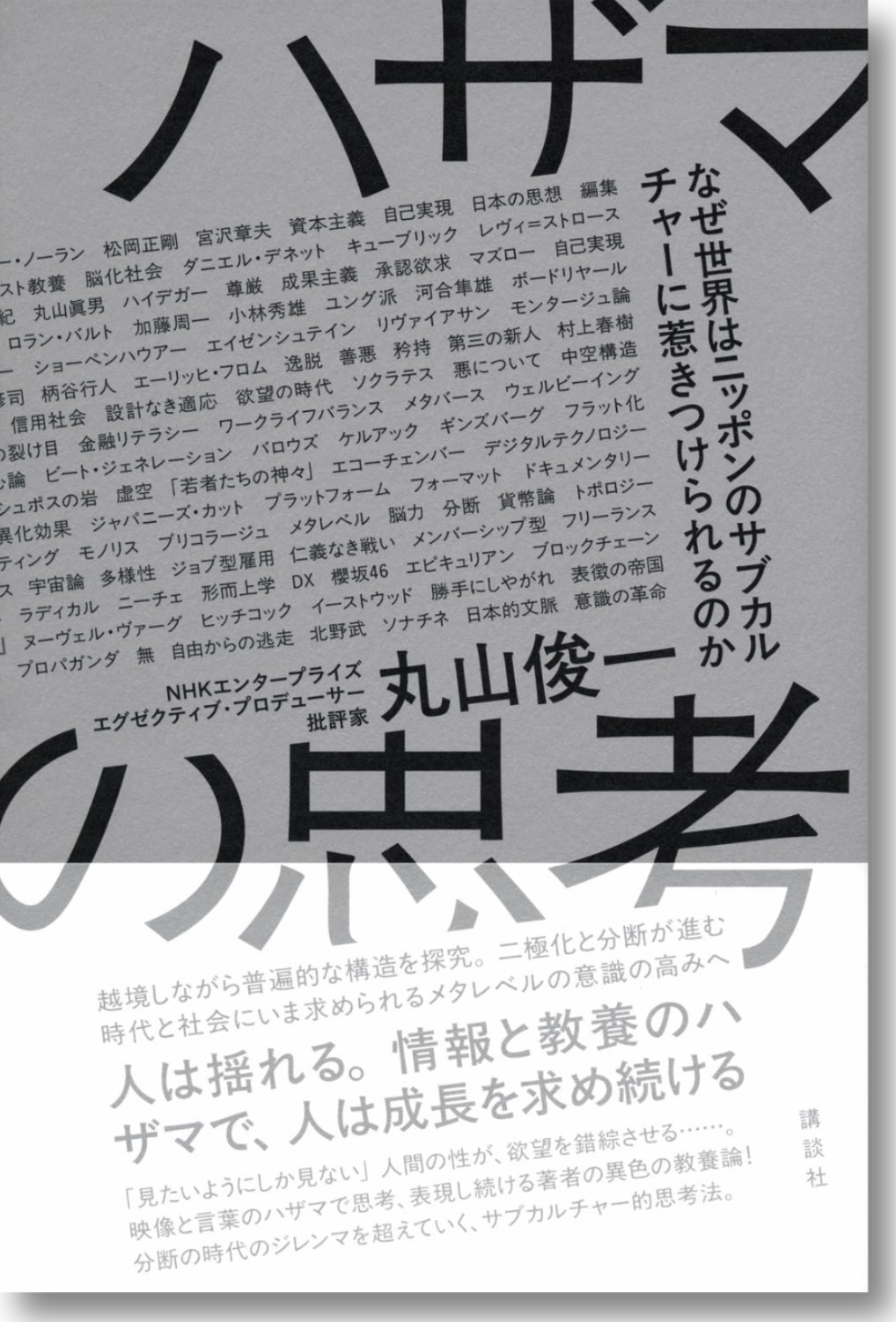
ハザマの思考
なぜ世界はニッポンのサブカルチャーに惹きつけられるのか
「欲望の資本主義」「ニッポン戦後サブカルチャー史」など、異色の教養ドキュメンタリー番組のプロデューサーとして知られる著者による、思考と観測の断想録。キーワードは「ハザマ」、つまり、何かと何かの「狭間(はざま)」に着目します。従来の枠組みがゆらぎ、混沌とする世の中で、割り切れなさやズレの発生地点に切り込むことが、人を惹きつけるコンテンツを生み出すことにつながっているのかもしれません。
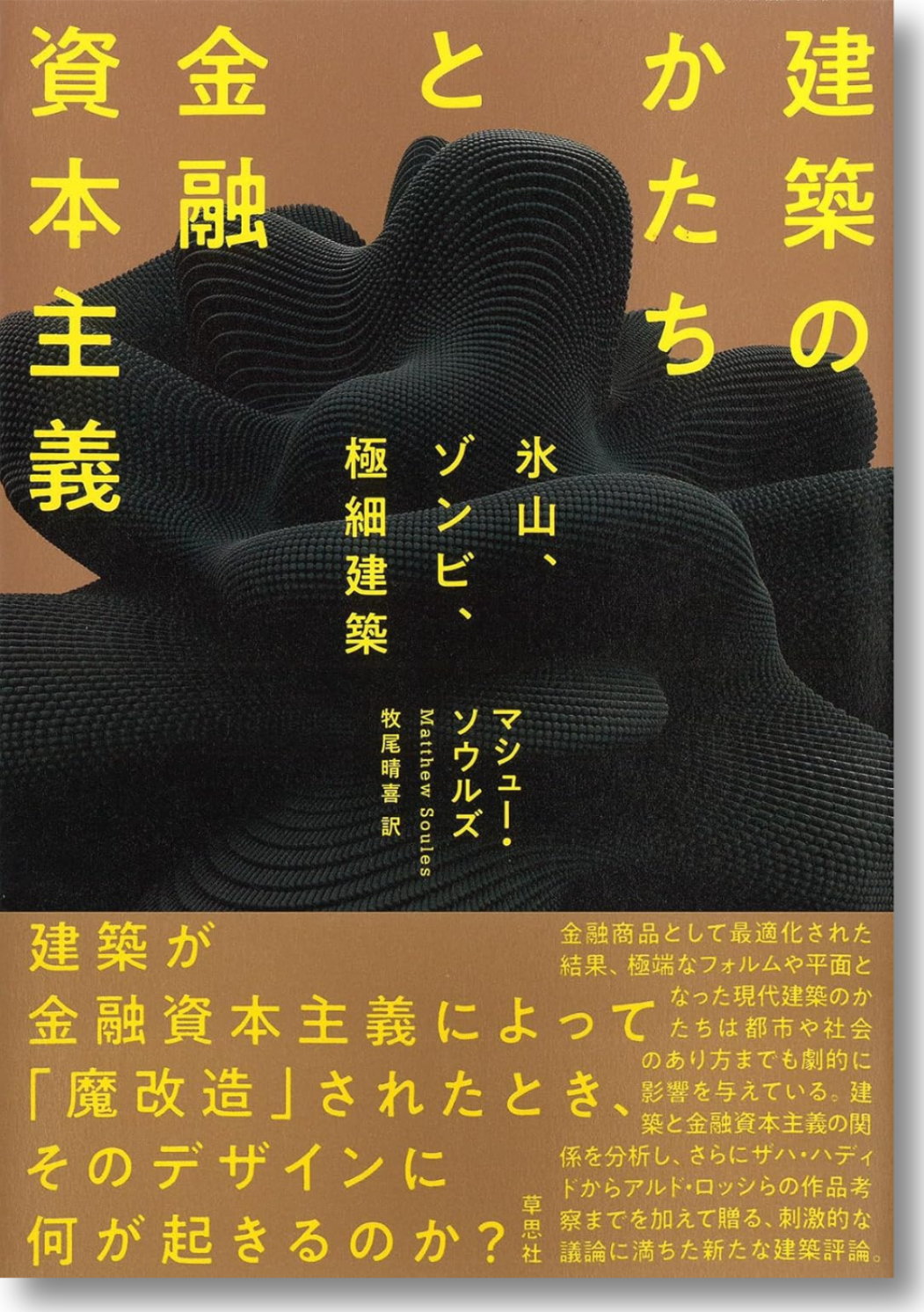
建築のかたちと金融資本主義
氷山、ゾンビ、極細建築
最新の技術と先端のデザインを取り入れた斬新で巨大な建築が作られる背景には、金融資本主義の見えざる手が存在している。地下に巨大な空間を持つ氷山建築、購入されても人が住んでいないゾンビ建築、極限まで高層化された極細建築などを事例に、金融資本主義がドライブする不気味なアーバニズムを描き出す刺激的な論考です。
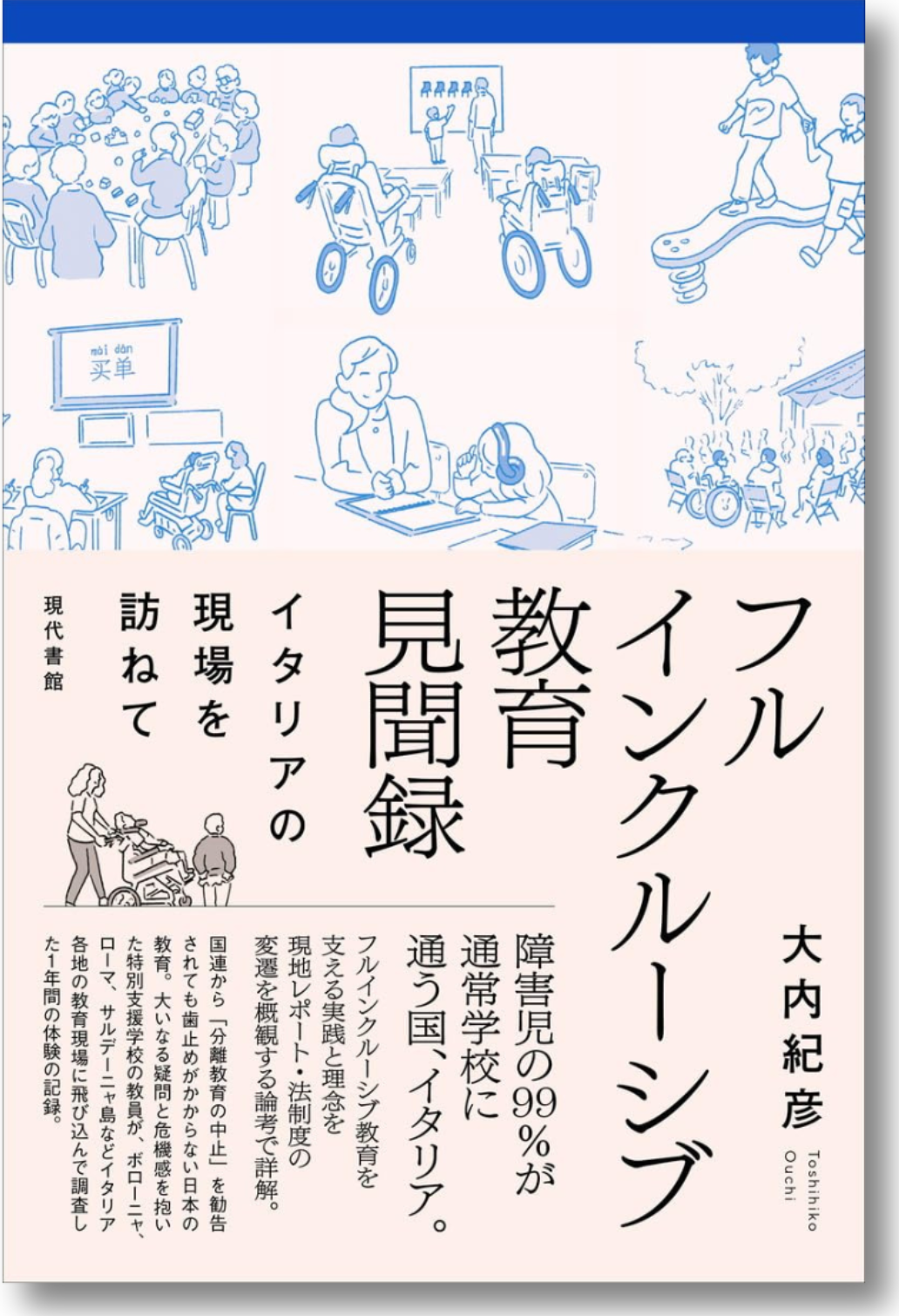
フルインクルーシブ教育見聞録
イタリアの現場を訪ねて
日本では「特別支援学級」や「特別支援学校」という制度によって、健常な子どもと障害を持った子どもは分離されて教育を受けるのが標準的ですが、イタリアでは99%以上の障害児が地域の学級で教育を受けているそうです。本書は特別支援学校教員である著者が、イタリアの現場に足を運び、見聞きしたことをまとめたもの。教育という観点のみならず、インクルーシブとは何かを考え、実現するためのヒントが詰まった一冊です。
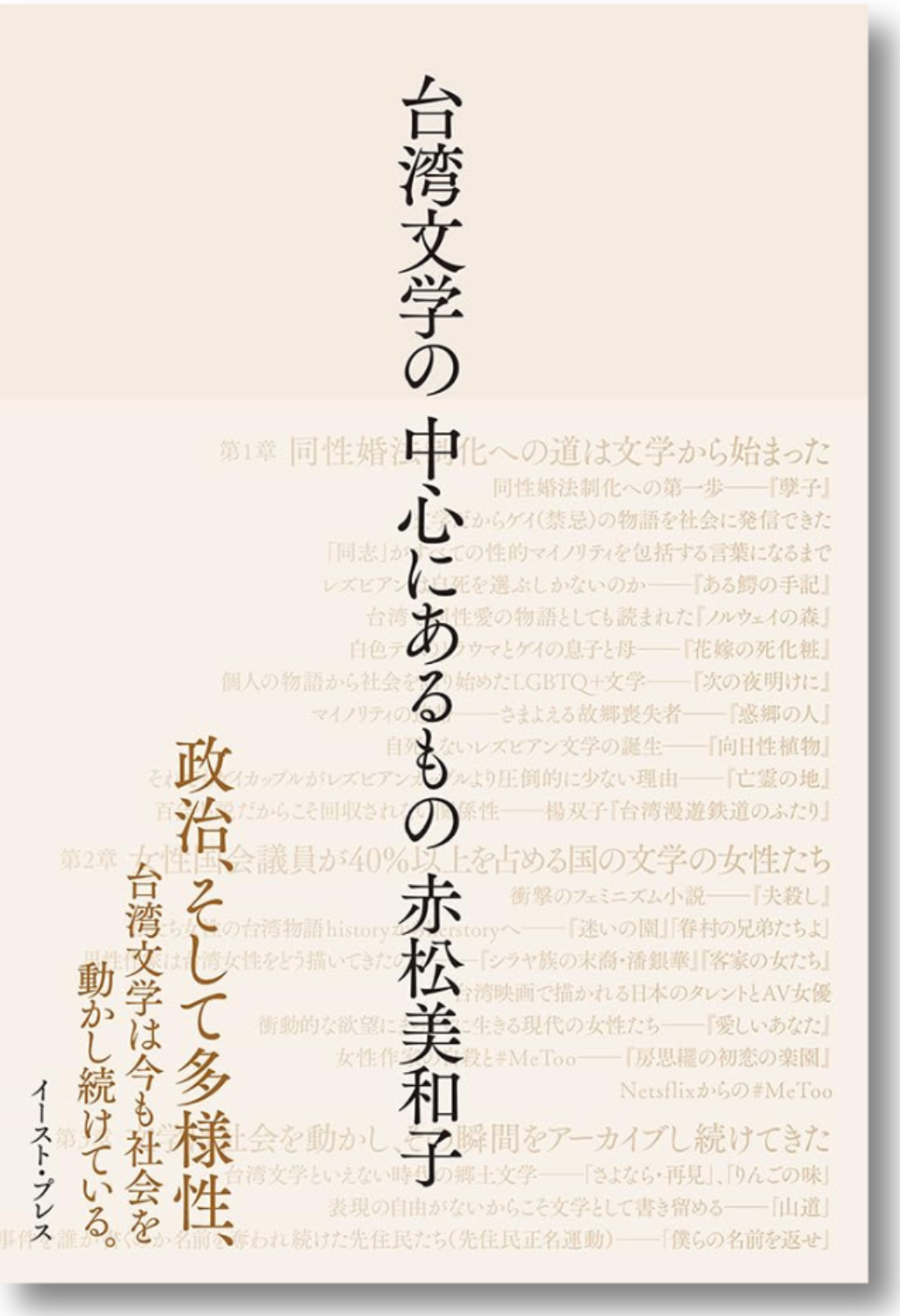
台湾文学の中心にあるもの
「台湾文学の中心にあるものは政治である」という書き出しで始まる本書。もちろん著者にそう決めつける意図はないのですが、著者自身も「台湾文学に出会った頃は、政治と文学の距離の近さに驚いた」と書いています。日本では馴染みの薄い台湾文学ですが、日本文学は台湾で親しまれているそう。著名な映画やドラマへの言及もあり、台湾の社会・文化の入り口にもなる一冊です。これを機に、台湾文学を手に取ってみたくなります。

アメリカの未解決問題
アメリカ在住のジャーナリスト竹田ダニエルと、米国政治外交史を専門とする三牧聖子による対談本。日本の大手メディアでは報道されない、2024年のアメリカ社会で起きた運動や論争について多方面に語られています。イスラエル・ガザの戦争、拡大する格差、政治的マイノリティの権利、などの一筋縄では行かない問題が絡み合ったまま、自国第一主義に邁進する現在のアメリカ。その未解決問題は、日本の社会とも無関係ではないはずです。
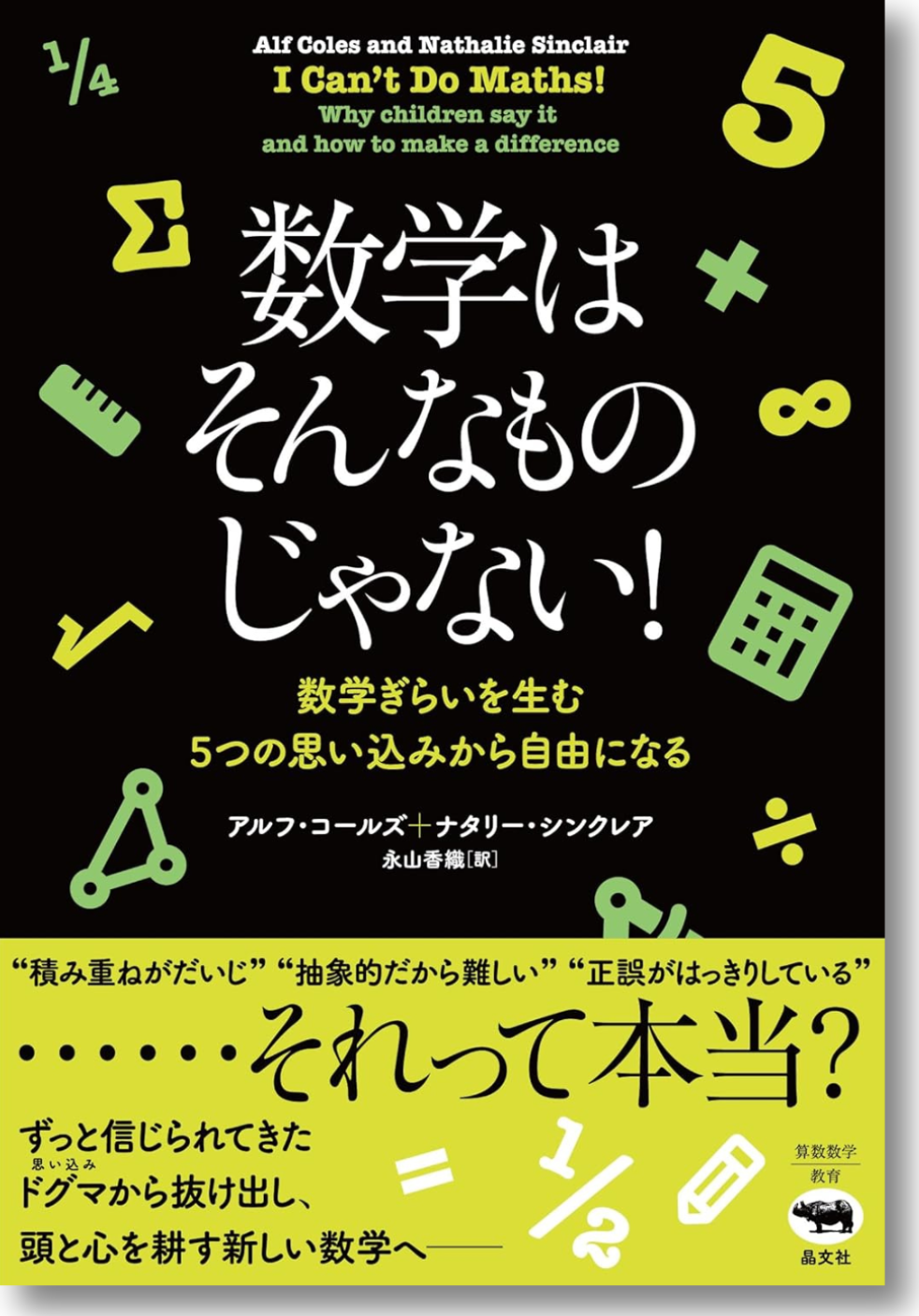
数学はそんなものじゃない!
数学ぎらいを生む5つの思い込みから自由になる
「数学は常に正しいか、間違っているか」「数学は才能のある人のもの」など、いつの間にか「数学とはこういうもの」と規定してしまいがち。そんな先入観を変えることを目指して本書は書かれています。数式などはほとんど登場せず、ものごとを読み解くツールとして数学の考え方を紹介してくれます。科学技術が重要性を増す社会の中で、文系・理系の枠組みにとらわれず、数学の学び方や役割について考えさせられる一冊。
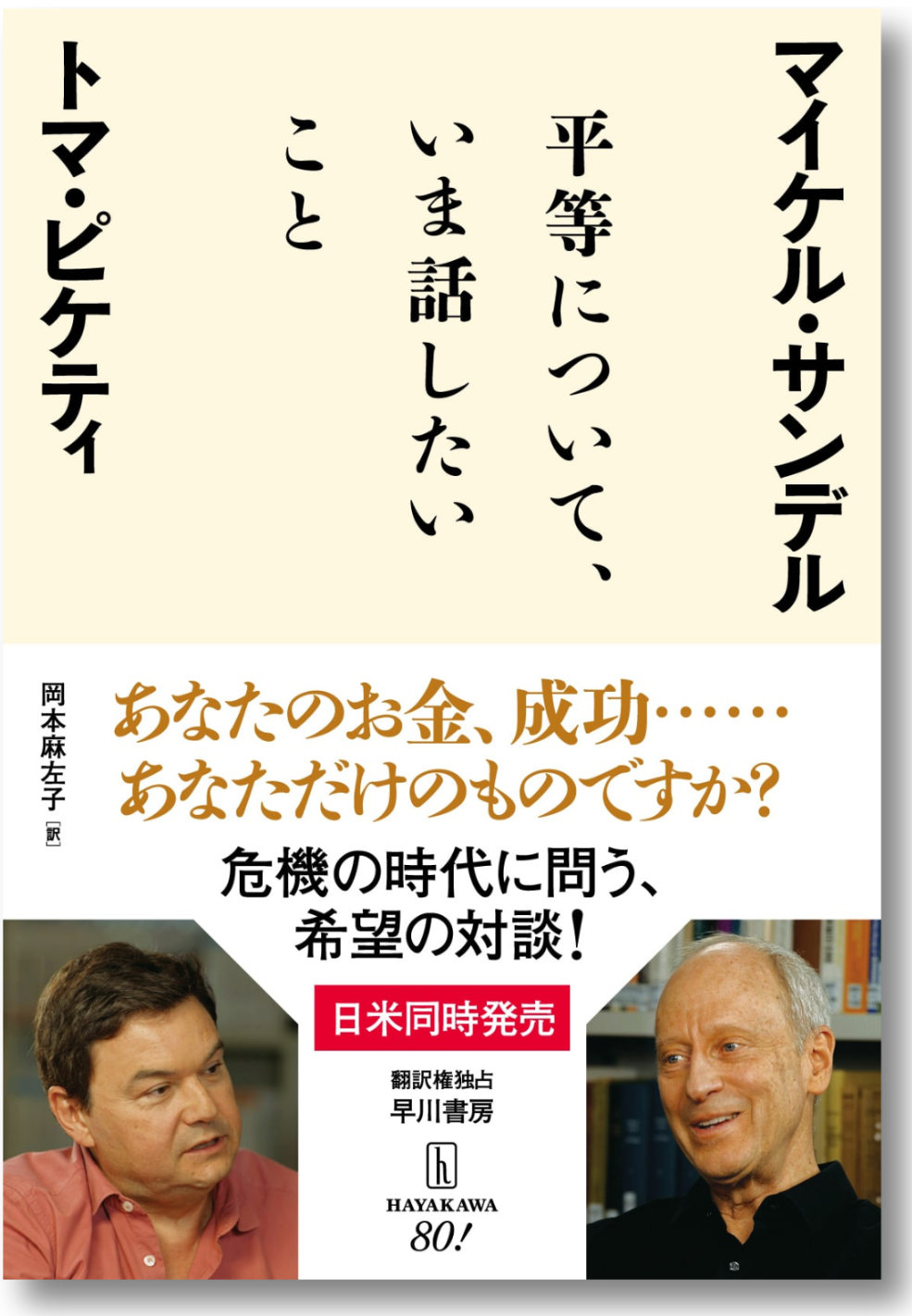
平等について、いま話したいこと
アメリカの政治哲学者マイケル・サンデルと、フランスの経済学者トマ・ピケティ。日本でもそれぞれの著書やテレビ番組を通じてよく知られた二人による、2024年5月にパリ経済学校で行われた対談の書籍化です。テーマは「平等」について。二人の学問的、文化的な背景の違いは、平等を思考する、あるいは実現するアプローチの違いとして対談に現れていきます。簡単に答えが出ないテーマだからこそ、領域横断的な議論の重要さに気付かされます。
会社と社会の読書会
畑中彰宏、若林恵、 山下正太郎、工藤沙希黒鳥社
責任と物語
戸谷洋志春秋社
人と人のあいだを生きる
播磨靖夫どく社
ハザマの思考
丸山俊一講談社
建築のかたちと金融資本主義
マシュー・ソウルズ草思社
フルインクルーシブ教育見聞録
大内紀彦現代書簡
台湾文学の中心にあるもの
赤松美和子イースト・プレス
アメリカの未解決問題
竹田ダニエル、三牧聖子集英社
数学はそんなものじゃない!
アルフ・コールズ、 ナタリー・シンクレア晶文社
平等について、いま話したいこと
トマ・ピケティ、 マイケル・サンデル早川書房
注目の記事
-
03月25日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年3月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の"いま"が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
03月25日 (火) 更新
aiaiのなんか気になる社会のこと
「aiaiのなんか気になる社会のこと」は、「社会課題」よりもっと手前の「ちょっと気になる社会のこと」に目を向けながら、一市民としての視点や選....
-
03月25日 (火) 更新
米大学卒業式の注目スピーチから得られる学び<イベントレポート>
ニューヨークを拠点に地政学リスク分析の分野でご活躍され、米国社会、日本社会を鋭く分析されているライターの渡邊裕子さんに、アメリカの大学の卒業....
現在募集中のイベント
-
開催日 : 05月19日 (月) 12:30~14:15
ジェラルド・カーティス氏 特別講演「これからの民主主義」
コロンビア大学政治学名誉教授のジェラルド・カーティス氏をお迎えし、トランプ政権の今後の展望と、これからの民主主義の可能性についてご講演いただ....