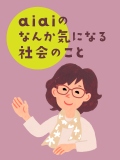記事・レポート
活動レポート
英語でレポートを書く力、議論する力を身につける
石倉洋子のグローバル・ゼミ(Global Agenda Seminar)2014の第2回レポート!
更新日 : 2014年08月20日
(水)
Session 2:Logical Communication
講師・ファシリテーター:石倉 洋子(一橋大学名誉教授)
文/小林 麻実 写真/スクール事務局

石倉 洋子(一橋大学名誉教授)

並ぶと「 I ♥ Mother Teresa 」になるTシャツで臨むチーム!
これからお迎えするゲスト講師の方々とのセッションを前に、まずは「安心の入門編」として、石倉洋子・一橋大学名誉教授から直接ロジカルシンキング等についてお教え頂く、第2回目のGAS(グローバル・ゼミ)。
まずは、初回にゼミ生から提出されたGlobal Issueについてのレポートを題材として、「What(何がissueなのか)」、「Why(どうしてそれが問題なのか)」、「How(どのように解決すべきか)」を明確に表現することの重要性や、それを実現するためのポイントをレクチャーして頂きました。
「英文レポートを書く際は、先に日本語で考えてから英訳すると、日本語の発想になってしまいます。ロジカルでなくなるし、時間もかかるので、英語でサマリーを作り、最初から英文で書き始めること。」等の石倉教授の具体的なアドバイスに、参加者の皆さんもレポートを作成した時の疑問点や不安に思っていることを、積極的に訊ねていきます。
そのような基本概念を理解したうえで、ディベートの形を取って、さらにロジカルに考える力をつけていきます。
今回のテーマは、「ネルソン・マンデラとマザー・テレサでは、どちらが世界にインパクトを与えたか?」と、「ホワイトカラー・エグゼンプションの導入に賛成か、反対か?」の2題。なかなか難しい、どちらが正解とはいえない問題ですが、敢えて賛否を決め、4つのチームに分かれて議論します。
「マンデラかマザーテレサか」の議論は「そもそもインパクトとは何か。質で計るのか量で計るのか」といった定義の問題から始まりました。これを自分たちに有利に決めてしまえば、議論の勝者となるところですが、相手とのやり取りの中で自分の意見を修正しながら説得していくということは、どちらのチームにとってもなかなか難しいようでした。
ホワイトカラー・エグゼンプションの賛否については、両チームともに、端的に論拠を提示しようと試みました。メリット、デメリットの何を重視するか、議論をどこまで広げるかという点について、その場で考えていかなくてはなりません。徹底したリサーチと事前の準備が、ディベートには欠かせないことが伺えます。
終了時にはどのチームも疲れ切った様子。しかし石倉教授が言われるように、このようなディベートは数を重ねることによって上手になるものです。確実に何かを身に付け、一歩進んだことがわかるセッションでした。
まずは、初回にゼミ生から提出されたGlobal Issueについてのレポートを題材として、「What(何がissueなのか)」、「Why(どうしてそれが問題なのか)」、「How(どのように解決すべきか)」を明確に表現することの重要性や、それを実現するためのポイントをレクチャーして頂きました。
「英文レポートを書く際は、先に日本語で考えてから英訳すると、日本語の発想になってしまいます。ロジカルでなくなるし、時間もかかるので、英語でサマリーを作り、最初から英文で書き始めること。」等の石倉教授の具体的なアドバイスに、参加者の皆さんもレポートを作成した時の疑問点や不安に思っていることを、積極的に訊ねていきます。
そのような基本概念を理解したうえで、ディベートの形を取って、さらにロジカルに考える力をつけていきます。
今回のテーマは、「ネルソン・マンデラとマザー・テレサでは、どちらが世界にインパクトを与えたか?」と、「ホワイトカラー・エグゼンプションの導入に賛成か、反対か?」の2題。なかなか難しい、どちらが正解とはいえない問題ですが、敢えて賛否を決め、4つのチームに分かれて議論します。
「マンデラかマザーテレサか」の議論は「そもそもインパクトとは何か。質で計るのか量で計るのか」といった定義の問題から始まりました。これを自分たちに有利に決めてしまえば、議論の勝者となるところですが、相手とのやり取りの中で自分の意見を修正しながら説得していくということは、どちらのチームにとってもなかなか難しいようでした。
ホワイトカラー・エグゼンプションの賛否については、両チームともに、端的に論拠を提示しようと試みました。メリット、デメリットの何を重視するか、議論をどこまで広げるかという点について、その場で考えていかなくてはなりません。徹底したリサーチと事前の準備が、ディベートには欠かせないことが伺えます。
終了時にはどのチームも疲れ切った様子。しかし石倉教授が言われるように、このようなディベートは数を重ねることによって上手になるものです。確実に何かを身に付け、一歩進んだことがわかるセッションでした。
注目の記事
-
04月22日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年4月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の"いま"が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
04月22日 (火) 更新
aiaiのなんか気になる社会のこと
「aiaiのなんか気になる社会のこと」は、「社会課題」よりもっと手前の「ちょっと気になる社会のこと」に目を向けながら、一市民としての視点や選....
-
04月22日 (火) 更新
米大学卒業式の注目スピーチから得られる学び<イベントレポート>
ニューヨークを拠点に地政学リスク分析の分野でご活躍され、米国社会、日本社会を鋭く分析されているライターの渡邊裕子さんに、アメリカの大学の卒業....
現在募集中のイベント
-
開催日 : 05月19日 (月) 12:30~14:15
ジェラルド・カーティス氏 特別講演「これからの民主主義」
コロンビア大学政治学名誉教授のジェラルド・カーティス氏をお迎えし、トランプ政権の今後の展望と、これからの民主主義の可能性についてご講演いただ....